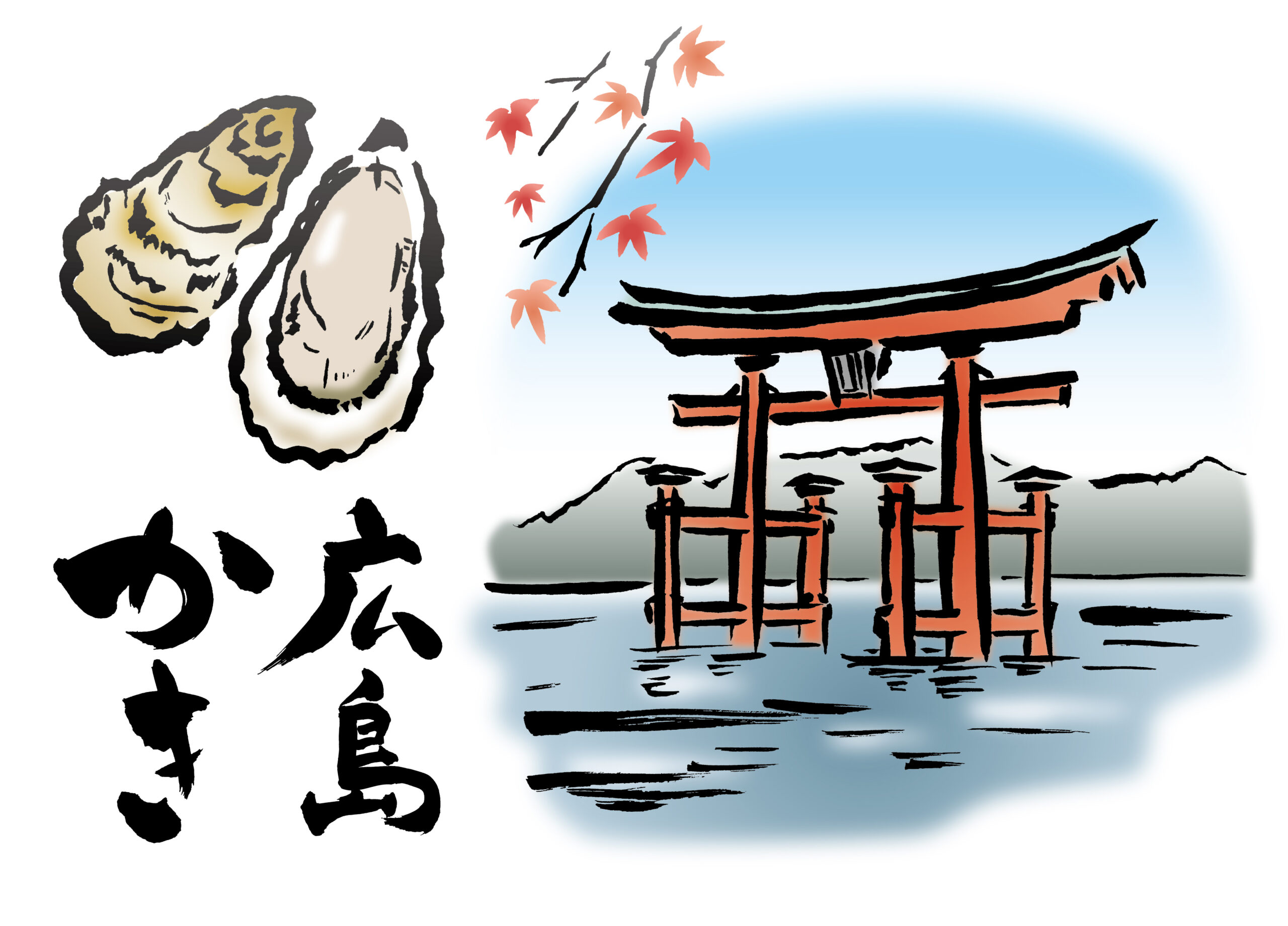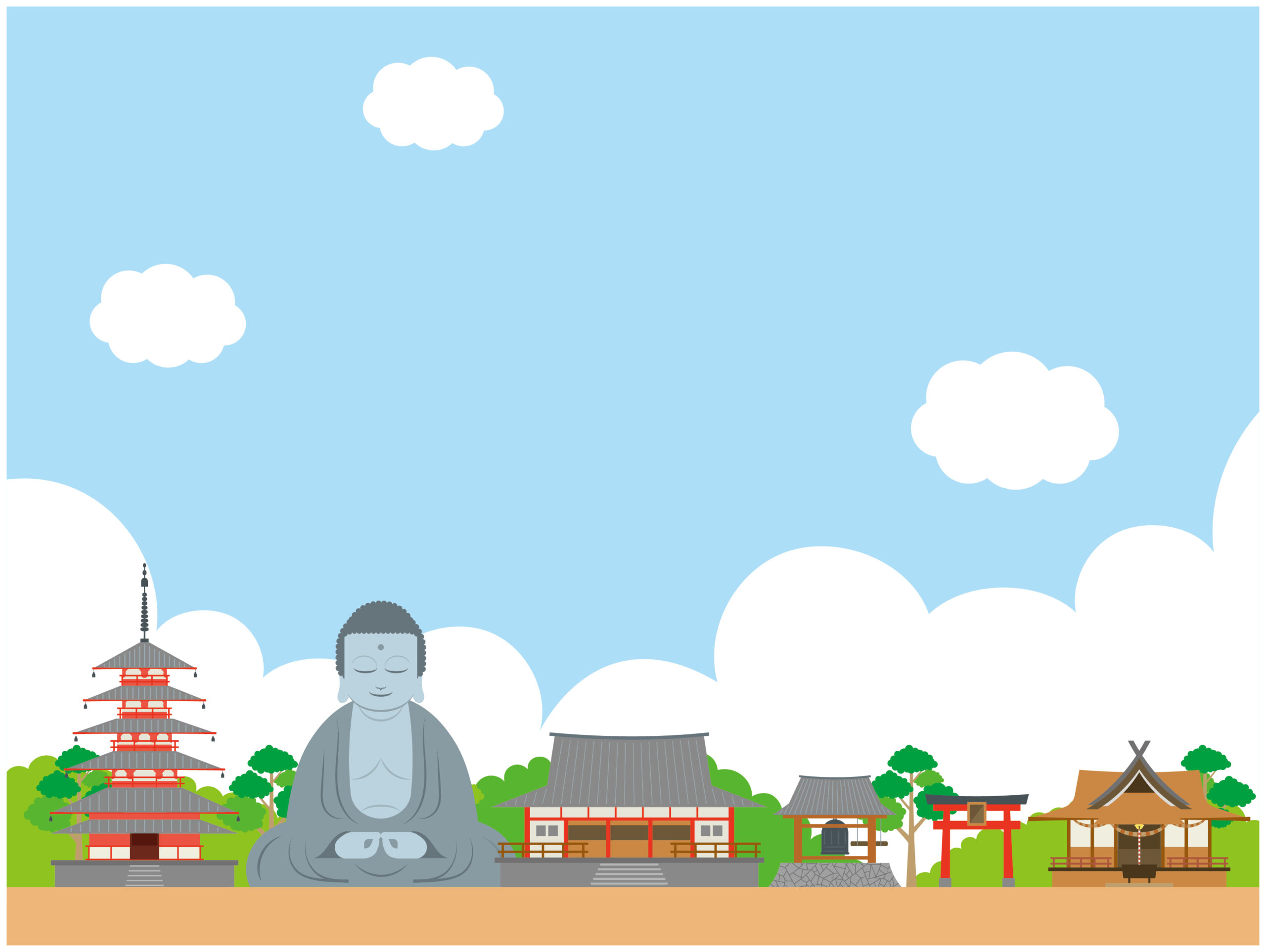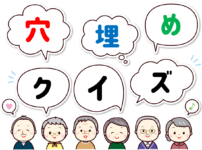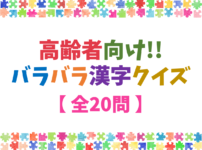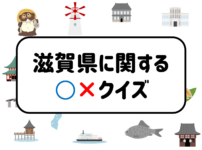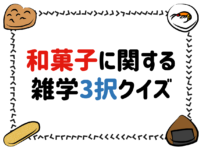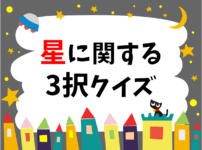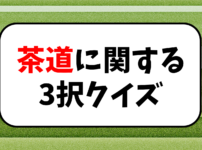博士
今回は都道府県のランキングクイズを出題するぞ!各都道府県の新たな魅力に気づくきっかけになるぞ!
【都道府県ランキングクイズ】高齢者向け!簡単&面白い三択雑学問題【前編10問】


博士
まずは10問出題するぞぉ!選択肢の中から正しいと思うものを一つ選ぶのじゃ!
第1問
リンゴの生産量が日本一多いのはどこでしょうか?
1.岩手県
2.長野県
3.青森県
+ 答えを見る(こちらをクリック)
3.青森県
リンゴの生産量日本一は、青森県です。
2019年(令和4年)のデータでは、全国のリンゴの生産量の合計は73万7100トンあり、そのうち約60%が青森県で作られています。
そんな青森県では、小学校に入学するとリンゴの品種が覚えられる下敷きが配られるなど、子どもから大人までリンゴに詳しい県でもあります。
第2問
国宝に指定された建造物の数が日本一多いのはどこでしょうか?
1.大阪府
2.京都府
3.奈良県
+ 答えを見る(こちらをクリック)
3.奈良県
国宝に指定された建造物の数が日本一多いのは、奈良県です。
奈良県には国宝に指定されている建造物が64件あります。
ちなみに、大阪府は5件、京都府は52件となっています。
第3問
小麦の生産量が日本一多いのはどこでしょうか?
1.北海道
2.沖縄県
3.静岡県
+ 答えを見る(こちらをクリック)
1.北海道
小麦の生産量日本一は、北海道です。
国産小麦の約6割が北海道産です。小麦は寒さに強い作物であり、世界的に見ても乾燥地帯や寒冷地域で栽培されてきました。
北海道には梅雨も無いため、小麦の栽培に適した土地と言えます。
また、小麦は大きく2つに分けることができます。
秋に種をまき、翌年の夏に収穫する「秋まき小麦」春に種をまき、同じ年の夏に収穫する「春まき小麦」です。
また、小麦の品種によってパンに多く使われる物、麺に多く使われる物に分かれています。
第4問
パイナップルの生産量が日本一多いのはどこでしょうか?
1.鹿児島県
2.高知県
3.沖縄県
+ 答えを見る(こちらをクリック)
3.沖縄県
パイナップルの生産日本一は、沖縄県です。
そもそもパイナップルは生産できる土地が国内でも限られており、沖縄本島や石垣島などでしか栽培されていません。
2021年(令和3年)の農林水産省のデータによれば、100%が沖縄県産です。
しかし、国内で流通しているパイナップルの多くはフィリピン産のものになっています。
また、パイナップルは1つの苗から1つしか実が採れず、収穫まで苗を植えてから2年かかるなど手間がかかる果物でもあります。
第5問
ワカメの生産量が日本一多いのはどこでしょうか?
1.岩手県
2.鳥取県
3.茨城県
+ 答えを見る(こちらをクリック)
1.岩手県
ワカメの生産量日本一は、岩手県です。
岩手県は昭和24年(1949年)から、ワカメの養殖が盛んに行われ国内生産の約36%を占めています。
実は岩手県はワカメが育つには理想的な環境です。
秋から冬にかけて北から流れ込む親潮から豊富な栄養分が得られ、南から流れ込む黒潮と混ざり合ってワカメの成長に適した水温が出来上がります。そんな激しい海流と冬の厳しい風波が美味しいワカメを育てるのには大切です。
第6問
ネギの生産量が日本一多いのはどこでしょうか?
1.岐阜県
2.石川県
3.千葉県
+ 答えを見る(こちらをクリック)
3.千葉県
ネギの生産量日本一は、千葉県です。
ネギは水はけの良い土壌を好む野菜です。千葉県には江戸川の氾濫でできた土壌があり、それがネギの栽培に適しているのが、千葉県でネギの生産量が多い理由の1つになります。
有名なブランドネギに「矢切りネギ」というものがあり、他のネギよりも太く甘みがあるのが特徴です。
一般市場に出回ることは少ないのですが、贈答用としての人気もあります。
第7問
マツタケの生産量が日本一多いのはどこでしょうか?
1.富山県
2.長野県
3.秋田県
+ 答えを見る(こちらをクリック)
2.長野県
マツタケの生産量が日本一多いのは、長野県です。
マツタケはその名の通り、アカマツという松の木の周りに生えてくるキノコです。
アカマツの樹齢が20年~30年になるとマツタケが生え始め、30年~40年が最も活発にマツタケが生えるようになり、70年以上になると衰えてきます。
特に長野県上田市は盆地になっており、松だけではなくマツタケの菌にとっても育ちやすい環境になっています。
第8問
食品サンプル(飲食店前に飾られているもの)の生産量が日本一多いのはどこでしょうか?
1.奈良県
2.岐阜県
3.静岡県
+ 答えを見る(こちらをクリック)
2.岐阜県
食品サンプルの生産量が日本一多いのは、岐阜県です。
約6割が岐阜県郡上市で作られており、食品サンプルの生みの親である岩崎瀧三さんも岐阜県郡上市出身です。
食品サンプルは蝋や合成樹脂で作られており、最初こそ業務用でしか流通していませんでしたが、近年では模型などとしての需要から一般向けにも販売されています。
第9問
柿の生産量が日本一多いのはどこでしょうか?
1.愛媛県
2.和歌山県
3.鳥取県
+ 答えを見る(こちらをクリック)
2.和歌山県
柿の生産量が日本一多いのは、和歌山県です。
正月飾りの「串柿」をご存じでしょうか。和歌山県は柿の名産地であるため、串柿の生産も盛んです。串柿とは、串に刺さった干し柿です。
四郷地区と呼ばれる地域では、400年程前から串柿の生産が盛んに行われてきました。
串柿は1本の竹串に10個の干し柿が刺さっています。2個、6個、2個の順に分かれ、「いつもニコニコ(2個2個)仲むつまじく(中6つ)」という願いが込められていると言われています。
第10問
シジミの水揚げ量が日本一多いのはどこでしょうか?
1.島根県
2.大分県
3.群馬県
+ 答えを見る(こちらをクリック)
1.島根県
シジミの水揚げ量日本一は、島根県です。
特に宍道湖で獲れるヤマトシジミは有名です。宍道湖は僅かに塩分を含む汽水湖であるため、魚介類が豊富に生息しています。
そんな豊かな環境で育ったシジミは大粒で肉厚です。
名産品である宍道湖シジミですが、獲り尽くしてしまうことがないように漁を行う時間や、1回の漁で獲ることができる重量の制限、漁を休む日などがしっかりと定められています。
漁の様子を観光で見に行きたい方は、時間や行われている曜日などを事前に確認すると良いでしょう。
【都道府県ランキングクイズ】高齢者向け!簡単&面白い三択雑学問題【中編10問】
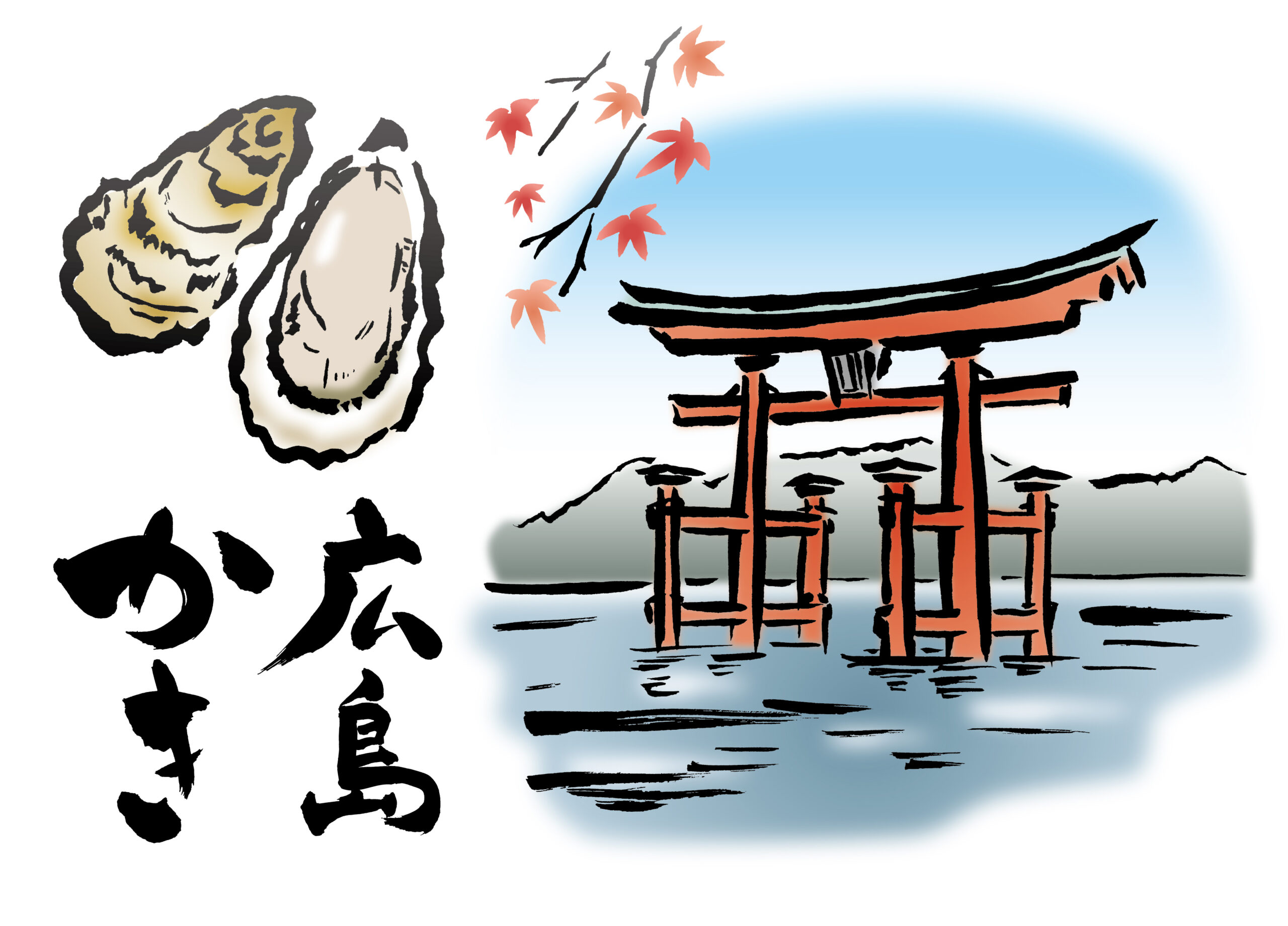

博士
前編10問はどうじゃったかのう?まだ物足りないという人は、次の10問にも挑戦してみるのじゃ!
第11問
温泉の源泉が日本一多いのはどこでしょうか?
1.神奈川県
2.群馬県
3.大分県
+ 答えを見る(こちらをクリック)
3.大分県
温泉の源泉が日本一多いのは、大分県です。
大分県と言えば別府温泉が有名ですが、県内ほぼ全ての市町村から温泉が湧き出ています。
大分県内の温泉の源泉数は4342ヶ所です。2位の鹿児島県が2773ヶ所であり、それを大きく引き離す数を見せています。
「大分に来れば、世界中の温泉地に行ったのと同じ」と言われる程であり、泥湯や砂湯など様々な入浴方法を楽しむことができます。
第12問
高齢化率が日本一高いのはどこでしょうか?
1.栃木県
2.秋田県
3.滋賀県
+ 答えを見る(こちらをクリック)
2.秋田県
高齢化率が日本一高いのは、秋田県です。
高齢化率とは、集団の中に65歳以上の人がどの程度の割合いるかを示したものです。
秋田県の高齢化率は、約39%となっています。秋田県に限らず若い世代が県外に働きに出るなどすると当然、高齢化率は上がっていくことになります。
全ての都道府県に言えることではありますが、少子高齢化が進む現代では高齢化率が上昇していく傾向にあります。このまま行くと秋田県の場合、2045年には約50%が高齢者になるとも言われています。
しかし、「高齢化が進んでいる=寝たきりの人が多い」とは限りません。高齢者でも元気に活気ある生活を送っている方も多くいます。年を重ねても元気で自分らしく過ごしていける期間「健康寿命」を少しでも伸ばしていくのが高齢化社会では重要になってきますね。
第13問
ニラの生産量が日本一多いのはどこでしょうか?
1.長崎県
2.熊本県
3.高知県
+ 答えを見る(こちらをクリック)
3.高知県
ニラの生産量が日本一多いのは、高知県です。
高知県は全国のニラの約27%を占めています。高知県の温暖な気候と長年積み重ねてきた研究がこの数値を示す結果へとつながっています。
高知県で栽培されたニラは、肉厚で柔らかく、香りが強いという特徴があります。ハウスと露地栽培が行われており、年間通してニラに適した環境の中での栽培が行われています。
ニラと豚肉を一緒に炒めた「ニラ豚」が高知県で定番のスタミナ料理になっています。
第14問
トマトの生産量が日本一多いのはどこでしょうか?
1.熊本県
2.広島県
3.奈良県
+ 答えを見る(こちらをクリック)
1.熊本県
トマトの生産量が日本一多いのは、熊本県です。
熊本県では同じ県内でも、温暖な海沿いでは秋~春にかけて、涼しい高原では夏~秋にかけてトマトの栽培が可能であるため、年間を通してトマトの生産が盛んに行われています。
中でも、土壌塩分濃度が高い土地で栽培される「塩トマト」は有名です。
普通のトマトは糖度が5~6くらいですが、塩トマトは糖度が8度以上であり、中には糖度10を超える物もあるなどフルーツのように甘いトマトです。オレンジが糖度10くらいであるため、単純な糖度だけで言えばそれに近い数値と言えます。
第15問
ウナギの養殖が日本一多いのはどこでしょうか?
1.静岡県
2.鹿児島県
3.宮崎県
+ 答えを見る(こちらをクリック)
2.鹿児島県
ウナギの養殖が日本一多いのは、鹿児島県です。
ウナギと言えば静岡県浜松市が有名ですが、静岡県は4位となっています(2位は愛知県、3位は宮崎県)。
昭和37年(1962年)にウナギの稚魚が不漁になったことで、ウナギの養殖業者が各地へ出ていったのがきっかけと言われています。
鹿児島県、特に大隅半島は温暖な気候と良質な地下水が豊富な環境でありウナギを育てるのに適しています。
また、ウナギの養殖と言えばウナギの稚魚を捕まえそれを育てるものです。
令和元年、近畿大学でウナギの人工ふ化が成功したことによりウナギの完全養殖も最早夢ではなくなりました。ちなみに天然のウナギの卵はいまだに発見されていません。
第16問
レモンの生産量が日本一多いのはどこでしょうか?
1.沖縄県
2.広島県
3.徳島県
+ 答えを見る(こちらをクリック)
2.広島県
レモンの生産量が日本一多いのは、広島県です。
レモンには寒さと強風雨によって感染する病気に弱い果物です。瀬戸内沿岸は、温暖な気候であり雨が少なく、台風による被害も少ない地域です。
国内でもレモンの成長にかなり適した環境である広島では、レモンの国内生産量の約6割を占めています。
ちなみに、レモンの香りは実よりも皮に多く含まれているため、レモン汁を絞る際には皮を下に向けて絞る方がより香りを楽しめます。
第17問
焼酎の出荷量が日本一多いのはどこでしょうか?
1.宮崎県
2.福岡県
3.埼玉県
+ 答えを見る(こちらをクリック)
1.宮崎県
焼酎の出荷量が日本一多いのは、宮崎県です。
宮崎県で作られる焼酎は、芋・米・麦・そばなど様々な原材料が使われているのも特徴です。
米、麦、サツマイモの生産量も宮崎県は比較的上位に来る数値を示しており、原材料を地元で確保できるのも大きな要素の1つでしょう。
2位は鹿児島県、3位は大分県となっており国内で生産される焼酎の約80%が九州で作られています。
第18問
米菓(煎餅やあられ)の生産量が日本一多いのはどこでしょうか?
1.岐阜県
2.宮城県
3.新潟県
+ 答えを見る(こちらをクリック)
3.新潟県
米菓の生産量が日本一多いのは、新潟県です。
流石は米どころといったところか、お米の生産量日本一の新潟県は米菓の生産量も日本一です。国内生産されている米菓の約5割が新潟県で生産されています。
三幸製菓、越後製菓などのお米を使った製品を扱う大手メーカーが複数あるのも、米どころである新潟県ならではと言えるでしょう。
第19問
お寺の数が日本一多いのはどこでしょうか?
1.京都府
2.愛知県
3.東京都
+ 答えを見る(こちらをクリック)
2.愛知県
お寺の数が日本一多いのは、愛知県です。その数はなんと約4600です。
お寺が多いイメージの京都は約3100であるため、お寺の数では意外にも大きな差があります。
かつて、尾張は寺を戦略上の防衛拠点として利用していたため寺を積極的に保護してきたなどとも言われていますが、なぜ愛知県にこんなにもお寺が多いのかをはっきり示す文献などは発見には至っていません。
第20問
納豆の1世帯あたりの消費量が一番多いのはどこでしょうか?
1.茨城県
2.福島県
3.三重県
+ 答えを見る(こちらをクリック)
2.福島県
納豆の生産量で言えば茨城県が1位なので消費量も…と思いますが、以外にも1位は福島県です。
その理由として考えられるのは、「福島県の山間部では昔から納豆が冬の貴重なたんぱく源として大切にされてきたこと」「1世帯あたりの人数が全国平均よりやや多いこと」などがあるとされています。
また、福島県では納豆を調理に使うことも多いようであり、調理に使用することでご飯にかけて食べるよりも多くの量を1度に消費しているのも理由と言えます。
【都道府県ランキングクイズ】高齢者向け!簡単&面白い三択雑学問題【後編10問】
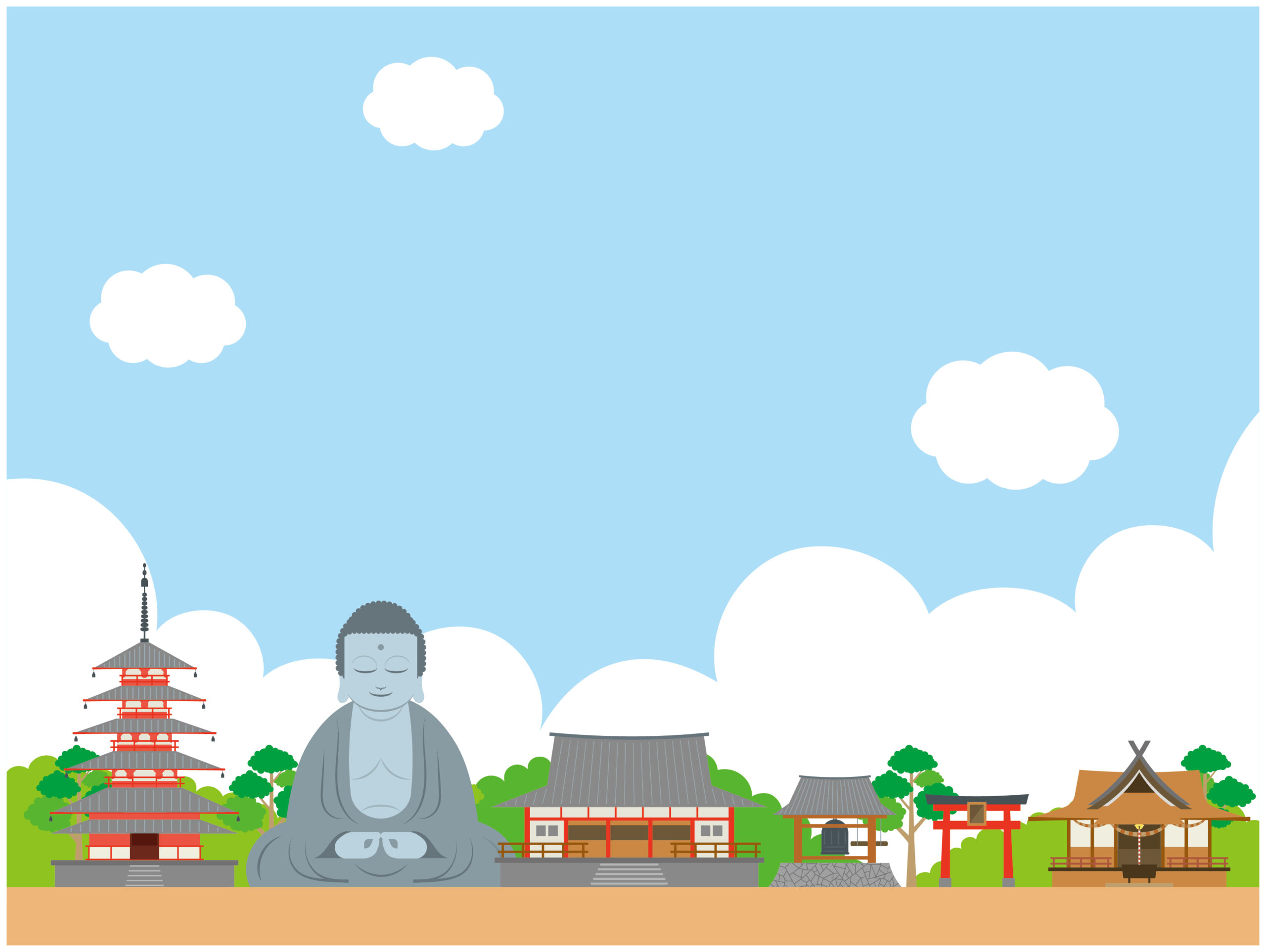

博士
中編10問はどうじゃったかのう?「まだまだ物足りない!」という人は、次の10問にも挑戦してみるのじゃ!
第21問
日本一高くまで噴き上がる噴水がある都道府県はどこでしょうか?
1.山形県
2.佐賀県
3.岡山県
+ 答えを見る(こちらをクリック)
1.山形県
日本一高くまで噴き上がる噴水は、山形県の寒河江ダムにある「月山湖大噴水」です。
水が112mの高さまで噴き上がるシンボル的な存在となっています。
なんと、世界全体で見ても水の噴き上がる高さでは第4位に入っています。
第22問
生糸の生産量が日本一の都道府県はどこでしょうか?
1.群馬県
2.山口県
3.長野県
+ 答えを見る(こちらをクリック)
1.群馬県
群馬県は生糸の生産量が日本一であり、国内生産の約69%を占めています。
なんと、1954年(昭和29年)からずっと1位を保っています。
第23問
日本一長い私道がある都道府県はどこでしょうか?
1.滋賀県
2.富山県
3.山口県
+ 答えを見る(こちらをクリック)
3.山口県
日本一長い私道は、山口県にある「宇部興産専用道路」です。
UBE三菱セメントという企業が保有しており、美祢市と宇部市を結ぶ全長31.94kmもある私道です。
昭和43年から全線開通まで14年の歳月をかけて建設されました。
第24問
人口10万人あたりのカレー屋の店舗数が日本一多い都道府県はどこでしょうか?
1.長野県
2.石川県
3.愛知県
+ 答えを見る(こちらをクリック)
2.石川県
石川県の人口10万人あたりのカレー屋の店舗は、8.47軒となっており日本一です。
石川県にはご当地カレーの「金沢カレー」があり、県内のみならず県外の人からも愛されるメニューとなっています。
第25問
シュウマイの消費量が日本一の都道府県はどこでしょうか?
1.北海道
2.神奈川県
3.福岡県
+ 答えを見る(こちらをクリック)
2.神奈川県
神奈川県はシュウマイの消費量が日本一です。
特に横浜市の平均年間支出金額は2,248円となっており、全国平均の1,039円の約2.16倍です。
やはり県内のみならず、観光客からの人気も高い崎陽軒の存在が大きいようです。
第26問
医薬品製剤出荷額が日本一の都道府県はどこでしょうか?
1.埼玉県
2.三重県
3.兵庫県
+ 答えを見る(こちらをクリック)
1.埼玉県
埼玉県は、医薬品製剤出荷額が約7,056億円で全国1位となっています。
化粧水の出荷額も約496億円で全国1位、乳液の出荷額も319億円で全国1位となっています。
埼玉県が日本の健康と美容を支えるための大きな役割を果たしていると言っても過言ではないでしょう。
第27問
爆竹の消費量が日本一の都道府県はどこでしょうか?
1.岩手県
2.京都府
3.長崎県
+ 答えを見る(こちらをクリック)
3.長崎県
長崎県は爆竹の消費量が日本一であり、国内の爆竹の約半数は長崎県で消費されていると言われています。
毎年8月に行われる「精霊流し」は、故人の精霊をあの世へ送り出すために、藁や木で作った船にお供え物を乗せて川や海に流す行事です。
その際に大量の爆竹が使われています。元々は精霊船が通る道を清めるための魔よけ的な意味があったようですが、近年では「とにかく派手にやろう」という考えが強くなっているようです。
第28問
ちくわの消費量が日本一の都道府県はどこでしょうか?
1.岐阜県
2.鳥取県
3.滋賀県
+ 答えを見る(こちらをクリック)
2.鳥取県
「都道府県民1人あたりが1年間にどのくらいのちくわを食べているのか」を調べると、全国平均は21.8本となっていますが、鳥取県で49.8本となっており日本一です。
トビウオのすり身で作った「あごちくわ」や、魚のすり身と豆腐を混ぜて作った「とうふちくわ」などが名産となっています。
第29問
プラモデルの出荷額が日本一の都道府県はどこでしょうか?
1.静岡県
2.東京都
3.徳島県
+ 答えを見る(こちらをクリック)
1.静岡県
静岡県にはプラモデルを販売する大手メーカーの本社や工場などがあることから、静岡県は国内のプラモデル出荷額の約9割を占めています。
第30問
マーガレットの生産量が日本一の都道府県はどこでしょうか?
1.広島県
2.栃木県
3.香川県
+ 答えを見る(こちらをクリック)
3.香川県
香川県は、キク科の植物であるマーガレットの生産量が日本一です。
主な生産地である三豊市北部に位置する荘内半島は、温暖な気候や日照時間の長さ、水はけのよい土壌などマーガレット栽培に適した条件が揃っています。

博士
今回のクイズ問題は以上じゃ!君は何問解けたかな?
このサイトではいろんな脳トレクイズを紹介しているから、ぜひ他のクイズにも挑戦してみるのじゃ!