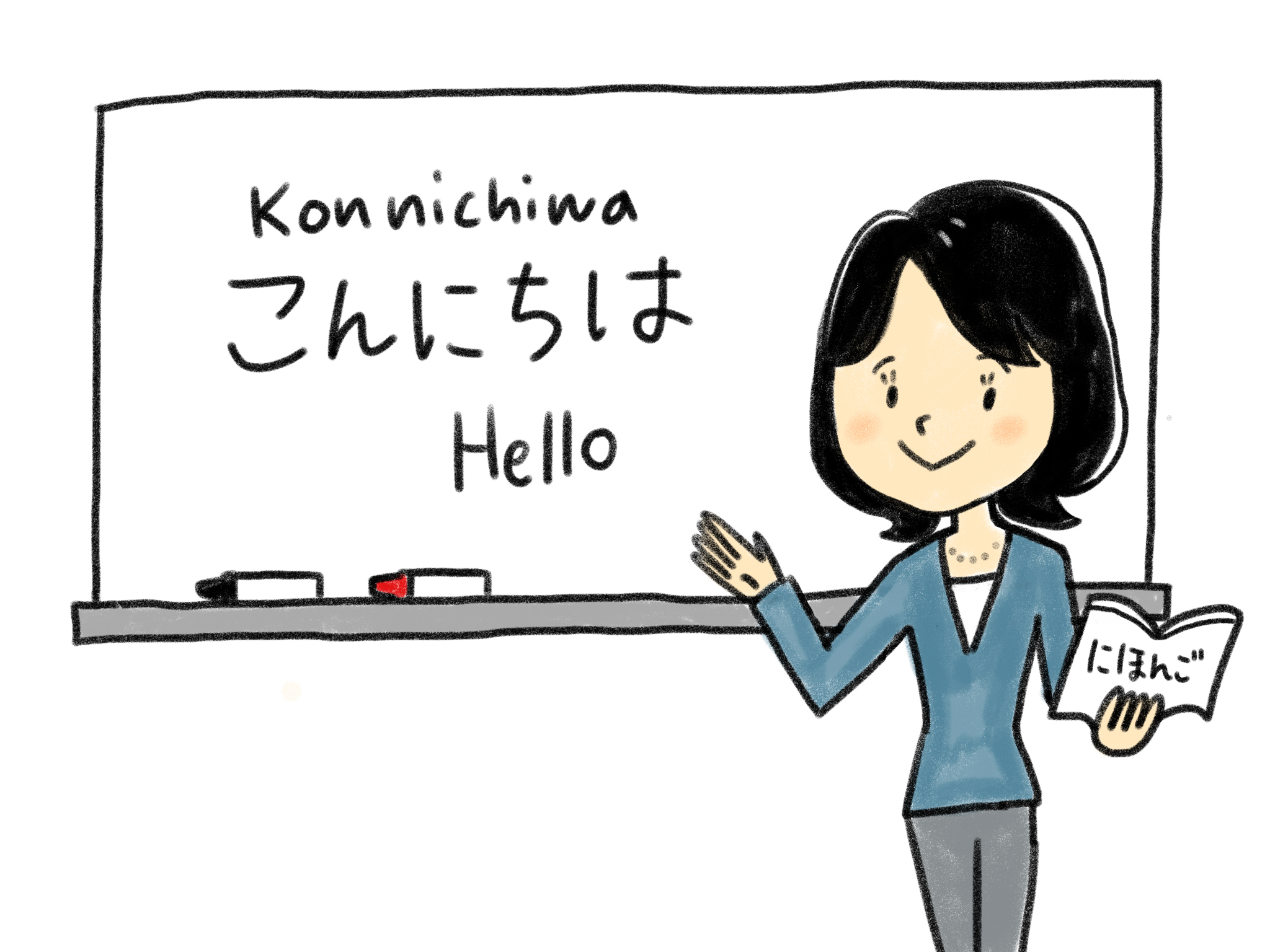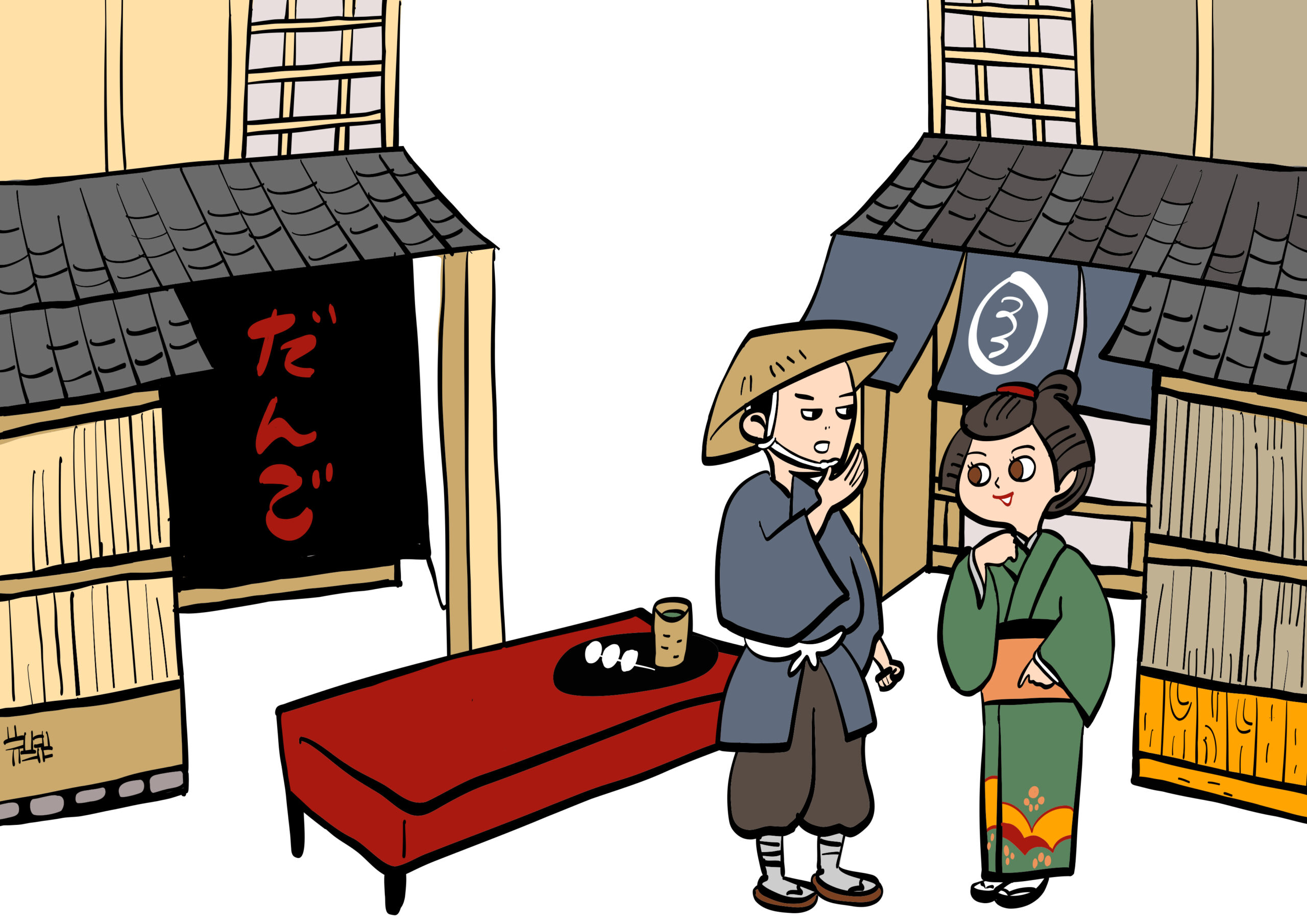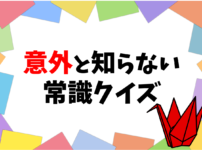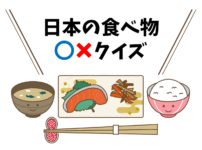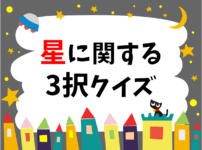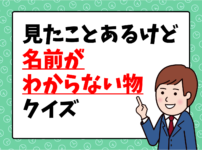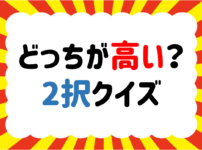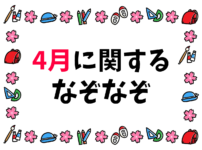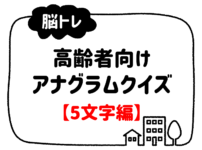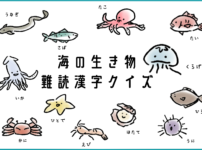博士
今回はおもしろい言葉の由来に関する語源クイズを紹介するぞ!全問正解目指して頑張るのじゃ。
【語源クイズ】面白い!タメになる言葉の由来に関する三択問題【前編10問】


博士
まずは10問出題するぞぉ!3つの選択肢の中から正解だと思うものを一つ選ぶのじゃ。
第1問
「チョコレート」の語源はなんでしょうか?
1.甘い板
2.黒い塊
3.苦い水
+ 答えを見る(こちらをクリック)
3.苦い水
チョコレートの語源は、メキシコ原住民の言葉で「苦い水」という意味の「chocolatre(ショコラトール)」です。
ショコラトールとは、カカオ豆と香辛料を使った飲み物で、メキシコ原住民の間で薬用飲料として飲まれていました。
当然ながら、砂糖もミルクも入っていないので甘くはなく、苦いものでした。
第2問
「黒幕」の語源となった日本の伝統芸能はなんでしょうか?
1.歌舞伎
2.落語
3.獅子舞
+ 答えを見る(こちらをクリック)
1.歌舞伎
黒幕とは、歌舞伎で舞台背景として闇を表現したり、場面が切り替わる際に用いる黒い幕のことです。
これを操作する人は裏方ではありますが、舞台にとって欠かせない存在です。
そんな裏で舞台を操る様子から、「陰で指図したり、裏で他者を操る人」を指す「黒幕」という言葉が生まれました。
第3問
「反りが合わない」の語源となったものはなんでしょうか?
1.刀
2.浴衣
3.下駄
+ 答えを見る(こちらをクリック)
1.刀
「反りが合わない」の「反り」は、刀の峰の反っている部分を指しています。
当然ではありますが、「反り」が鞘の形状と合わないと、刀を鞘に収めることができません。
その様子を人間関係にも例えるようになり、「考え方が一致せず、気心が合わないこと」を意味する「反りが合わない」という言葉が生まれました。
第4問
「ナルシスト」はある国の神話が語源となっています。
正しいものはどれでしょうか?
1.日本
2.ギリシャ
3.インド
+ 答えを見る(こちらをクリック)
2.ギリシャ
ギリシャ神話に登場する美少年ナルキッソスが、「ナルシスト」の語源となっています。
ナルキッソスは、エーコーという妖精の求愛を拒んだ罰として、神様に「泉に映った自分の姿に恋をする」という呪いをかけられました。
どうしても想いを遂げることができない彼はやつれ果て、泉に写った自分に接吻をしようとして、そのまま落下して溺死してしまいました。
この物語が元となり、「自己陶酔型の人」を「ナルシスト」と言うようになりました。
第5問
「アリバイ」の語源はなんでしょうか?
1.他の場所に
2.多忙な
3.他の人と一緒に
+ 答えを見る(こちらをクリック)
1.他の場所に
「アリバイ」の語源は、英語の「alibi」です。元はラテン語の「alius ibi」であり、「他の場所に」という意味があります。
日本では、大正時代に江戸川乱歩などによる探偵小説がブームを迎えました。
その頃から、「犯行時刻にその場にいなかったという証明」を指す言葉として、「アリバイ」が広まっていきました。
第6問
「油を売る」の語源となったエピソードとして正しいものはどれでしょうか?
1.油売りは何もしなくても儲かっていた
2.石油王は働かなくても生きていけるくらい財産がある
3.油売りが世間話をしながら油を売っていた
+ 答えを見る(こちらをクリック)
3.油売りが世間話をしながら油を売っていた
江戸時代、油を売り歩く「油売り」という職業がありました。
油売りは柄杓を使い、客が用意した容器に油を移す形で販売していました。
しかし、油は粘性が高く移すのに時間がかかってしまいます。その間、ずっと無言でいるわけにもいかず、油売りは客と世間話をしていました。
これが転じて「仕事を怠け、無駄話をする様子」を表す「油を売る」という言葉が生まれました。
しかし、実際の油売りは決して怠けて世間話をしていたわけではありませんでした。
第7問
「人間ドック」の語源はなんでしょうか?
1.大広間
2.船渠(せんきょ)
3.運河
+ 答えを見る(こちらをクリック)
2.船渠(せんきょ)
船渠とは、船舶を建造または修繕するための場所のことです。
オランダ語では、船渠のことを「dok(ドック)」と言います。
そのことから、人間が健康状態の検査をする様子をドックに入って整備点検する船に例えるようになりました。
第8問
「ゴリ押し」の語源となった生き物はなんでしょうか?
1.ゴリラ
2.ゴリという魚
3.ゴリという虫
+ 答えを見る(こちらをクリック)
2.ゴリという魚
鮴(ゴリ)とは、カジカや小型のハゼ類などを指す地方名です。
鮴は、吸盤状の腹ビレで川底にへばりつくように生息しています。そのため、漁の際には網が川底を削るように、力を込めて引く必要があります。
なかなか強引な漁の方法であることから、「無理にでも自分の思うところを押し通そうとすること」を指す「ゴリ押し」という言葉が生まれました。
第9問
山に登った時に叫ぶ「ヤッホー」という言葉の語源となったのは、どの国の言葉でしょうか?
1.ドイツ
2.中国
3.オーストラリア
+ 答えを見る(こちらをクリック)
1.ドイツ
「ヤッホー」は、ドイツ語の「JOHOO(ヨッホー)」という掛け声が語源となっています。
これは、ヨーロッパの登山家たちが使っていた掛け声です。
それが昭和初期に日本に伝わった際に、「ヤッホー」に変化して現在に至っています。
第10問
「急がば回れ」の語源となった観光地として、正しいものはどれでしょうか?
1.富士山
2.信濃川
3.琵琶湖
+ 答えを見る(こちらをクリック)
3.琵琶湖
昔、滋賀から京都に行く手段は「琵琶湖を船で渡る」か、「琵琶湖を徒歩で迂回していく」かの2択でした。
船の方が近道なのですが、山から吹き下ろす強風で船が転覆する危険がありました。さらに、強風で船を出す事すらできない日もありました。
陸路だと遠回りではありますが、風に左右されないルートであったことから「急がば回れ」ということわざが生まれました。
【語源クイズ】面白い!タメになる言葉の由来に関する三択問題【中編10問】
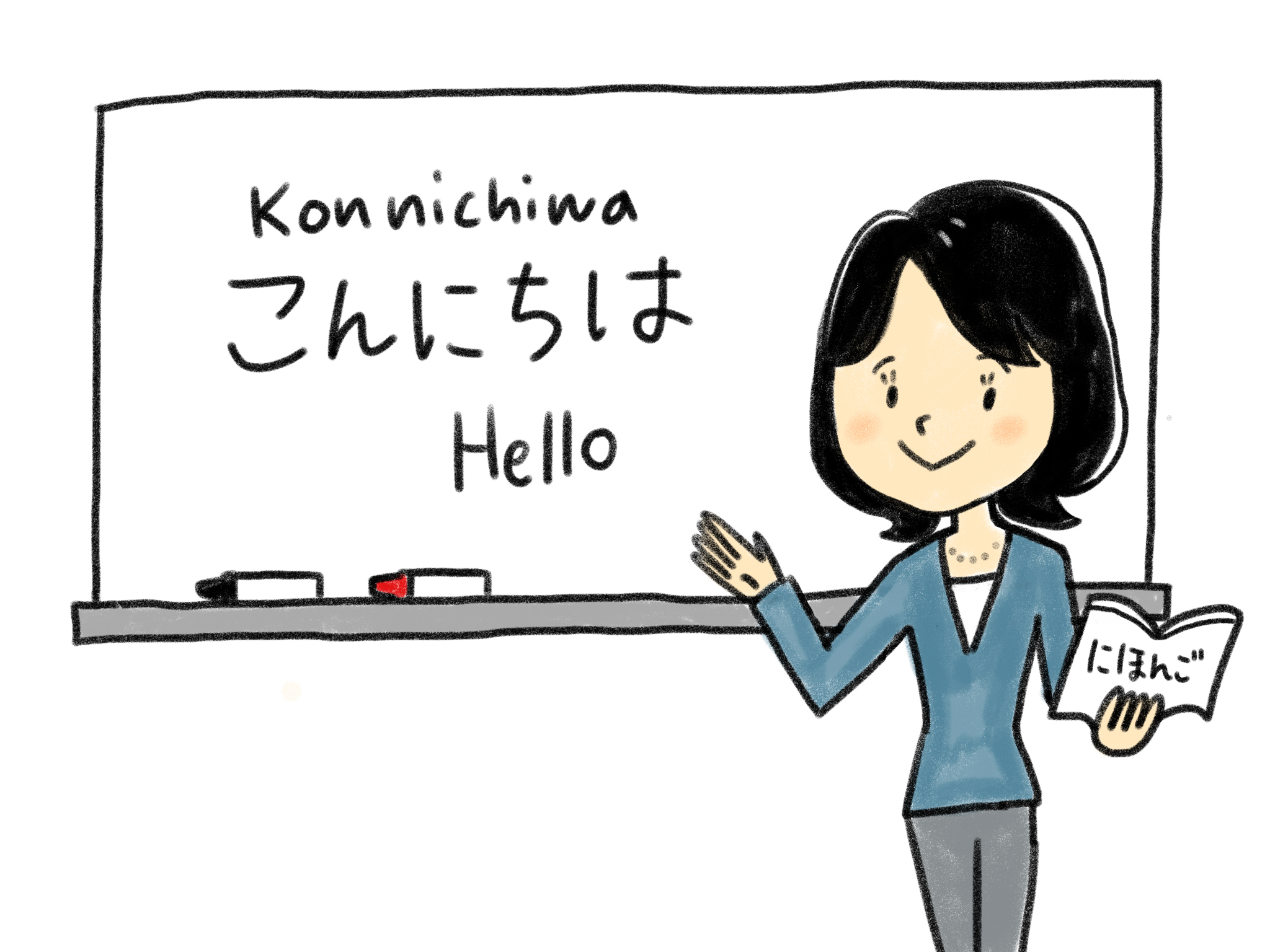

博士
前編10問はどうじゃったかのう?まだ物足りないという人は、次の10問にも挑戦してみるのじゃ!
第11問
「足を洗う」の語源となった職業はなんでしょうか?
1.町奉行
2.忍者
3.僧侶
+ 答えを見る(こちらをクリック)
3.僧侶
裸足で外を歩いていた修行僧が汚れた足を洗い、俗世間の煩悩を洗い清めていたことから「足を洗う」という言葉が生まれました。
それが転じて、「悪行を辞めること」を表す言葉となりました。
第12問
「ばったもん」の語源はなんでしょうか?
1.昆虫のバッタ
2.格安商品
3.野球のバッター
+ 答えを見る(こちらをクリック)
2.格安商品
「ばったもん」は、粗悪品や偽物のブランド品を指す言葉です。
しかし、最初はそのような意味ではなく「格安商品」という意味で使われていました。
昔、商品を格安で販売する店があり、そのような店は「バッタ屋」と呼ばれていました。しかし、バッタ屋の商品は正規のルートで仕入れていない怪しいものでした。
そのことから、次第に「粗悪品・偽物」という意味を持つようになりました。
第13問
「駄目」の語源はなんでしょうか?
1.囲碁
2.将棋
3.麻雀
+ 答えを見る(こちらをクリック)
1.囲碁
「駄目」とは、双方の境にあってどちらの地にも属さない所を指します。
そこに石を置いても自分の地とならないことから、「やっても甲斐のないこと」「やってはいけないこと」を指す言葉として使われるようになりました。
第14問
「シカト」の語源はなんでしょうか?
1.トランプ
2.花札
3.メンコ
+ 答えを見る(こちらをクリック)
2.花札
花札の10月の札に書かれている鹿は、そっぽを向いているようにも見えます。
そのため、「鹿十(しかとお)」から「シカト」に変化し、「無視すること」を表す言葉になりました。
第15問
「紅一点」の語源となった花はなんでしょうか?
1.桜
2.ザクロ
3.バラ
+ 答えを見る(こちらをクリック)
2.ザクロ
ザクロの花は、真っ赤で綺麗なとても目立つ花です。
緑が生い茂る中に真っ赤なザクロの花が咲いていると非常によく目立ちます。
このことから「同じようなものが並ぶ中、ひときわ目立つもの」を指す言葉として「紅一点」が使われるようになりました。
それが転じて現在では、「男性の中に女性が一人だけいる状況」として使われています。
第16問
「とどのつまり」の語源は魚です。
その魚とはなんでしょうか?
1.ボラ
2.カツオ
3.ヒラメ
+ 答えを見る(こちらをクリック)
1.ボラ
出世魚であるボラは、「オボコ→イナッコ→スバシリ→イナ→ボラ→トド」と成長するにつれて名前を変えていきます。
「トド」はこれ以上大きくならないことから「結局」「行き着くところ」を意味する「とどのつまり」という言葉が生まれました。
第17問
「カスタネット」の語源はなんでしょうか?
1.二枚貝
2.拍手
3.栗
+ 答えを見る(こちらをクリック)
3.栗
カスタネットは、スペイン語で栗を意味する「castaña(カスターニャ)」が語源となっています。
その名の由来には、「見た目が栗に似ているから」という説や、「栗の木を使って作られていたから」という説があります。
第18問
「図星」の語源はなんでしょうか?
1.梅干し
2.矢を射る的
3.星座占い
+ 答えを見る(こちらをクリック)
2.矢を射る的
「図星」とは、矢を射る的の中心にある黒い点のことです。
この図星を狙って矢を射ることから、「狙いどころ」という意味で使われるようになりました。
それが転じて、「人の指摘などが、まさにそのとおりであること」という意味でも使われるようになりました。
第19問
「エクレア」の語源として正しいものはどれでしょうか?
1.突風
2.稲妻
3.大雪
+ 答えを見る(こちらをクリック)
2.稲妻
「エクレア」の語源は、フランス語で「稲妻」を意味する「エクレール」です。
その名の由来は諸説あり、「焼いた表面にできる割れ目が稲妻に似ているから」「稲妻が落ちるのと同じくらい一瞬で食べられてしまうから」などといった説があります。
第20問
「サバを読む」の語源はなんでしょうか?
1.魚の鯖
2.フランス語で「元気?」という意味の「ça va(サバ)」
3.酒場
+ 答えを見る(こちらをクリック)
1.魚の鯖
年齢を若く言ったり、数を誤魔化すことを「鯖を読む」と言います。
鯖は傷みやすい魚であるため、冷蔵庫などが無い時代はできるだけ早く売りたい魚でもありました。
販売時にはスピードが重要視され、目分量で取引されることも多くありました。
そのため、魚屋が売ったと思った数と、実際に買い手の元にある鯖の数が合わないことが多発していました。
それが転じて、「都合のいい数字に誤魔化す」といった意味で「鯖を読む」という言葉が使われるようになりました。
【語源クイズ】面白い!タメになる言葉の由来に関する三択問題【後編10問】
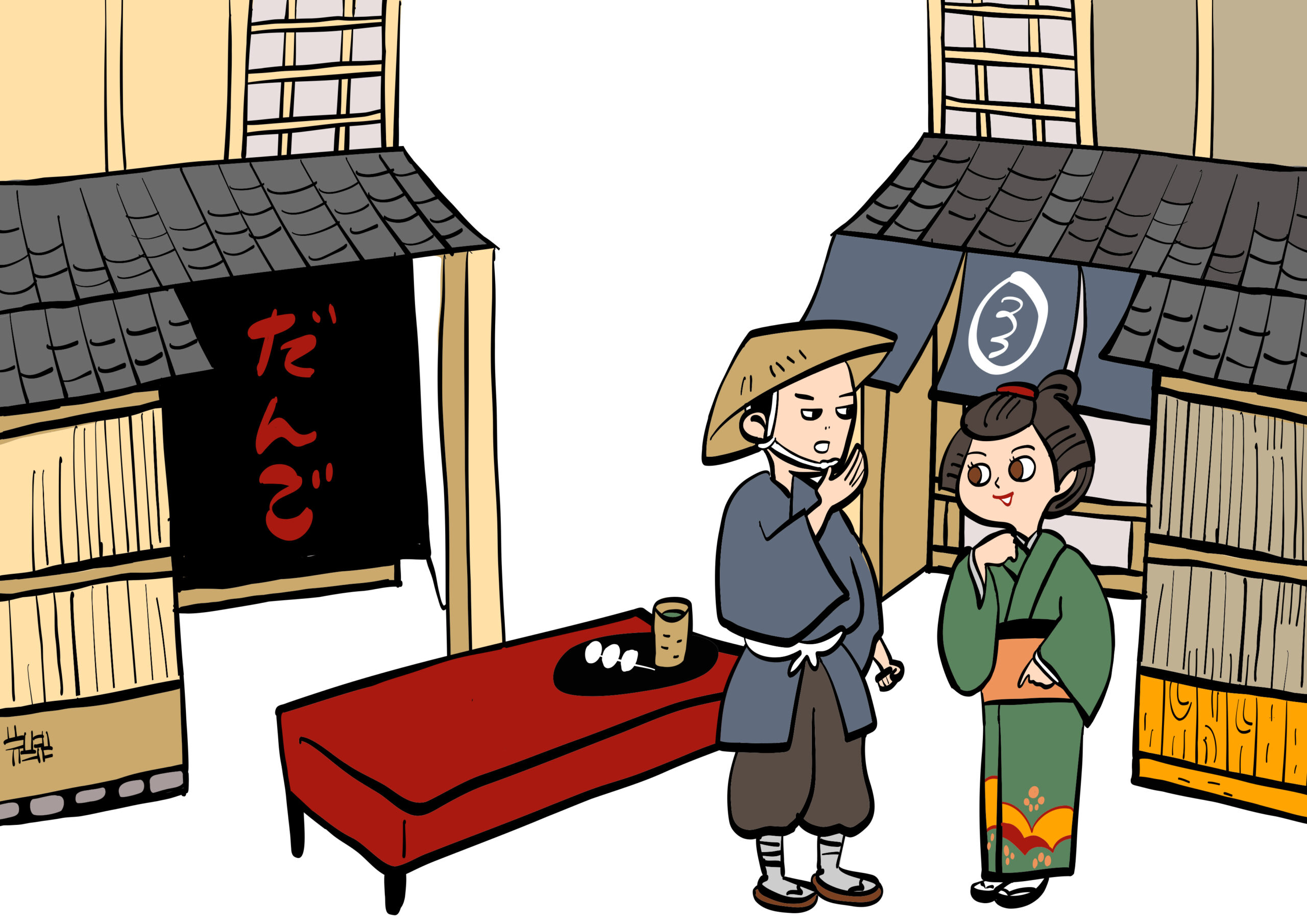

博士
中編10問はどうじゃったかのう?「まだまだ物足りない!」という人は、次の10問にも挑戦してみるのじゃ!
第21問
「金時豆」の語源はなんでしょうか?
1.坂田金時
2.時は金なり
3.昔あった寺院の名前
+ 答えを見る(こちらをクリック)
1.坂田金時
坂田金時は、源頼光の四天王の一人として平安時代に活躍したと言われる武将です。
坂田金時はいつも赤い顔をしていたため、赤いものを「金時」と例えるようになったのが由来だと言われています。
ちなみに…坂田金時の幼少期をモデルにした昔話が誰もが知っている「金太郎」です。
第22問
「テンパる」の語源はなんでしょうか?
1.麻雀
2.将棋
3.チェス
+ 答えを見る(こちらをクリック)
1.麻雀
麻雀であと1つで上がれる状態のことを「聴牌(テンパイ)」といい、これに「る」を付けて動詞にしたものが「テンパる」です。
つまり本来は、「あと一歩の状態」を指す言葉だったと言えます。
それがいつしか変化して「心に余裕がない様子」を表すようになりました。
第23問
「ビビる」の語源はなんでしょうか?
1.馬が駆け抜ける音
2.床が軋む音
3.鎧が触れ合った音
+ 答えを見る(こちらをクリック)
3.鎧が触れ合った音
「ビビる」の語源は、平安時代にまで遡ります。
大軍が動いて鎧が触れ合った時に「ビンビン」という音が響くことから、それを「びびる音」と表現したのが始まりだと言われています。
第24問
「面白い」の語源にはいくつかの説があり、そのうちの1つが神話の神様が関係しているというものです。
正しいものはどれでしょうか?
1.大黒天
2.天照大御神
3.火之迦具土神
+ 答えを見る(こちらをクリック)
2.天照大御神
日本神話には、天照大御神が天岩戸に隠れてしまい、世界が真っ暗になったという「岩戸隠れ」の伝説があります。
物語の中では天照大御神を外へ出そうと八百万の神々が天岩戸の外で宴会を開き、その騒ぎが気になった天照大御神は少しずつ天岩戸を開けて外の様子を伺います。
その時に闇に包まれていた世界がパッと明るくなり、戸の前にいた神々の顔(面)が白くはっきり見えるようになったことが由来だという説があります。
第25問
「ダッフルコート」の語源はなんでしょうか?
1.海外の医者の名前
2.海外の都市の名前
3.海外の商店の名前
+ 答えを見る(こちらをクリック)
2.海外の都市の名前
「ダッフルコート」の語源は、ベルギーの都市「Duffel(デュフェル)」だと言われています。
この町は毛織物を産業としており、極寒の海で働く漁師の作業着として作られたコートが「ダッフルコート」の始まりだとされています。
第26問
「ケバブ」の語源はなんでしょうか?
1.美味い肉
2.安い肉
3.焼いた肉
+ 答えを見る(こちらをクリック)
3.焼いた肉
「ケバブ」は、中東とその周辺地域で供される肉・魚・野菜などをローストして調理する料理の総称です。
ペルシャ語の「kabab」が語源であり、「焼いた肉」や「炙った肉」を指しています。
第27問
「ガチンコ」の語源はなんでしょうか?
1.相撲
2.柔道
3.合気道
+ 答えを見る(こちらをクリック)
1.相撲
力士どうしが激しく身体をぶつけた際に出る「ガチン!」という音が由来とされており、それほど激しく身体をぶつけ合うことから「真剣勝負」を意味するようになりました。
第28問
「にっちもさっちも」の語源はなんでしょうか?
1.金槌
2.そろばん
3.風呂桶
+ 答えを見る(こちらをクリック)
2.そろばん
「にっちもさっちも」は、元々はそろばんに関係する言葉であり、漢字では「二進も三進も」と書きます。
「二進」「三進」はそれぞれ「2÷2」「3÷3」を意味しており、2や3で割り切れることを表します。
そこから「2でも3でも割り切れず、計算が合わないこと」を「二進も三進も行かない」と表現するようになったのが始まりだとされています。
第29問
「馬が合う」の語源はなんでしょうか?
1.騎馬戦
2.馬車
3.乗馬
+ 答えを見る(こちらをクリック)
3.乗馬
乗馬では馬と乗り手の息を合わせることが重要です。
馬と乗り手の息がぴったり合っていることを人間同士にも当てはめたことが由来となっています。
第30問
「ドローン」の語源はなんでしょうか?
1.ミツバチ
2.ワシ
3.ヘリコプター
+ 答えを見る(こちらをクリック)
1.ミツバチ
「ドローン」は、「雄のハチ」を意味する英語「drone」が語源となっています。
プロペラの風を切る音がハチの羽音に似ていることが由来となっています。

博士
今回のクイズ問題は以上じゃ!君は何問解けたかな?
このサイトではいろんな脳トレクイズを紹介しているから、ぜひ他のクイズにも挑戦してみるのじゃ!