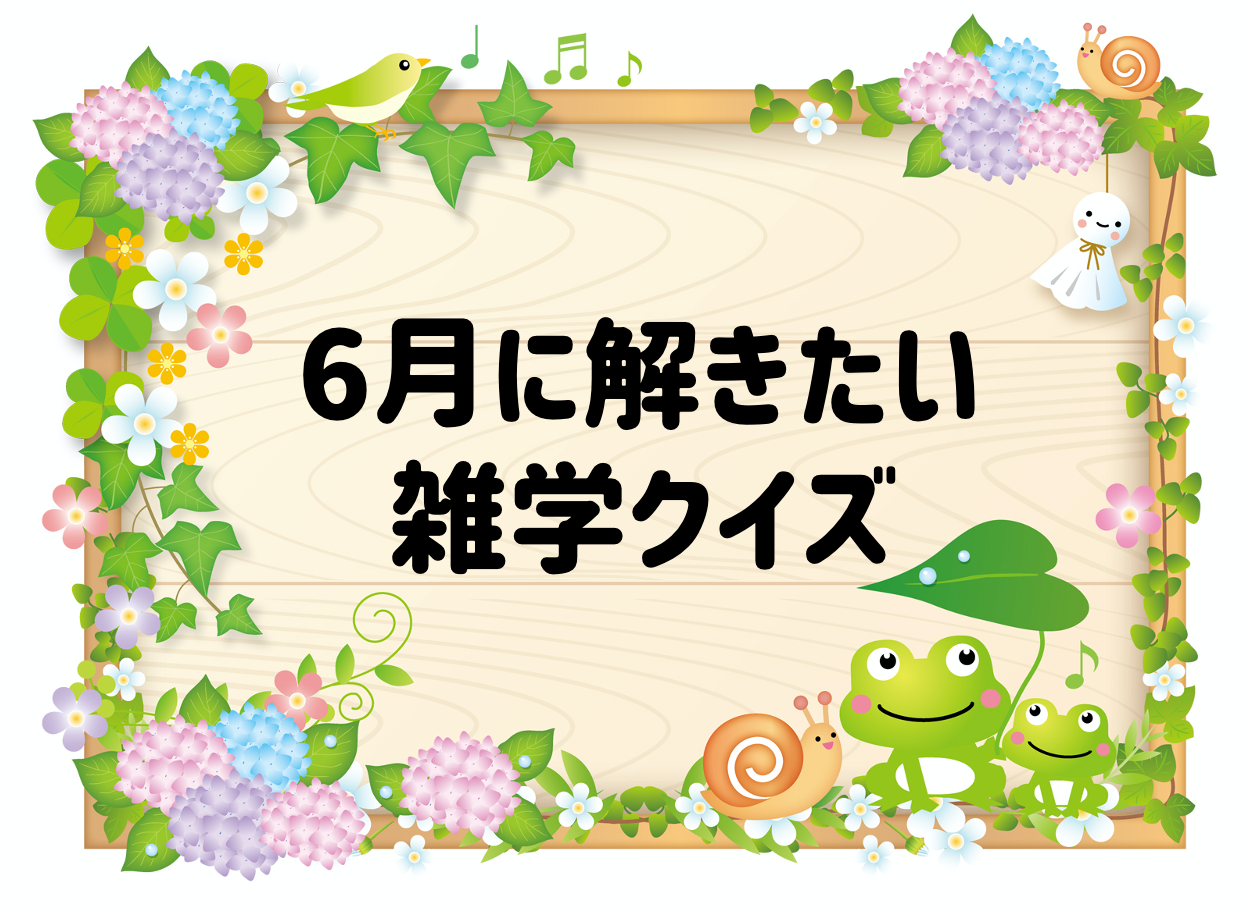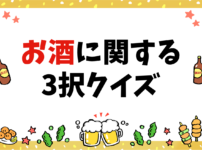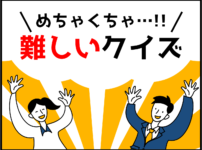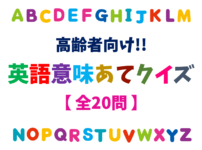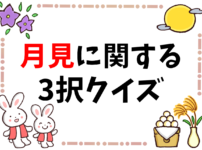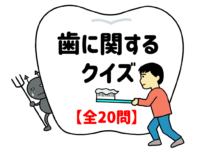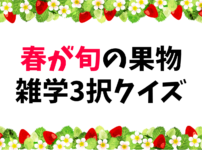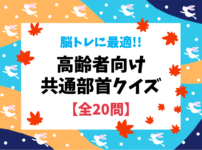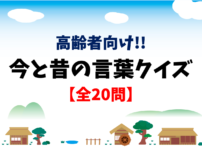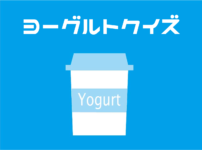博士
今回は6月に関する雑学クイズを紹介するぞ!知っておくと周りに自慢できるかも知れないぞぉ。ぜひ挑戦してみるのじゃ!
【高齢者向け】6月の雑学&豆知識クイズ問題【前編10問】


博士
まずは10問出題するぞぉ!3つの選択肢を出すから正解だと思うものを一つ選ぶのじゃ。
第1問
6月と言えば、『梅雨(つゆ)』です。
なぜ漢字では『梅雨』と書くようになったのでしょうか?
1.梅が熟す時期だから
2.普段の2倍以上雨が降る(倍雨)から梅雨となった
3.詳しいことは分かっていない
+ 答えを見る(こちらをクリック)
1.梅が熟す時期だから
梅が熟す頃に降る恵みの雨であることから、『梅雨』と表記されるようになったと言われています(※最も有力な説です)。
他にも以下のような説があります。
- この時期は湿度が高くカビが生えやすいことから『黴雨(ばいう)』と呼ばれていたものが同じ音の『梅雨(ばいう)』に変化した
- この時期は『毎』日のように雨が降ることから、『梅』という字が当てられた
第2問
梅雨時によく見かける「カタツムリ」。
カタツムリは藻や野菜、キノコなどを食べますが、他にもある意外なものを食べています。
それは一体なんでしょうか?
1.泥
2.ザリガニ
3.コンクリート
+ 答えを見る(こちらをクリック)
3.コンクリート
カタツムリが食べる意外なものは、コンクリートです。
カタツムリの殻は生まれた時からついている体の一部であり、炭酸カルシウムという成分で出来ています。
カタツムリが殻を維持・形成するためには、炭酸カルシウムを摂取する必要があります。
雨にさらされたコンクリートからは炭酸カルシウムが染み出してくるため、カタツムリはこれを摂取していると言われています。
第3問
ナメクジに塩をかけると縮むという話は有名ですが、カタツムリに塩をかけるとどうなるでしょうか?
1.縮む
2.膨張する
3.何も起きない
+ 答えを見る(こちらをクリック)
1.縮む
カタツムリに塩をかけると、ナメクジと同じように縮みます。
カタツムリやナメクジの体は90%以上が水分です。体の表面は常に粘液を出し続けることで潤いを保っています。そこに塩をかけると『浸透圧』というものが発生します。
体の表面の塩分濃度が濃くなるとそれを薄めようとして体の中から水分を出します。
その結果、体のほとんどが水分であるカタツムリやナメクジの体は、大量の水を出すので縮んでしまいます。
第4問
梅雨時に綺麗に咲く「アジサイの花」。
実はある条件によって青い花が咲くか、ピンクの花が咲くかが決まります。
その条件とは一体なんでしょうか?
1.土の温度が20℃以上か、19℃以下か
2.土が酸性かアルカリ性か
3.農薬を与えるか与えないか
+ 答えを見る(こちらをクリック)
2.土が酸性かアルカリ性か
アジサイは、酸性の土だと青い花、中性~アルカリ性の土だとピンクの花になります。
日本の土壌にはアルミニウムという成分が豊富に含まれています。このアルミニウムは酸性の土だと水に溶けやすく、中性~アルカリ性の土では水に溶けにくい性質を持っています。
酸性の土の場合、水に溶け込んだアルミニウムがアジサイの根から吸収。アルミニウムとアジサイが持つ『アントシアニン』という色素と結合すると、花が青色になります。
また、アントシアニンは本来赤い色素です。中世~アルカリ性の土ではアルミニウムが水に溶けにくいのでアジサイの根から吸収されず、花の色もアントシアニン本来の色が活きた赤やピンク色になります。
第5問
雨具の『合羽(かっぱ)』は、なぜそのような名前になったでしょうか?
1.河童から授かったという伝承があるから
2.外来語に漢字を当てはめたから
3.生産地名が『合羽』だった
+ 答えを見る(こちらをクリック)
2.外来語に漢字を当てはめたから
『合羽』はポルトガルから伝わったものであり、ポルトガル語の『capa』が元になった外来語です。
合羽は後に付けられた当て字であり、江戸時代頃から使われるようになりました。
第6問
世界初の折りたたみ傘はどこで生まれたでしょうか?
1.イギリス
2.日本
3.ドイツ
+ 答えを見る(こちらをクリック)
3.ドイツ
1928年(昭和3年)、世界で初めて折りたたみ傘がドイツのブランド、『Knirps(クニルプス)』より発売されました。
『Knirps』は現在では折りたたみ傘そのものを指す言葉になっています。
第7問
梅雨時に元気に鳴いている「カエル」。
そんなカエルの舌の長さはどのくらいと言われているでしょうか?
1.体の3分の1
2.体と同じ長さ
3.体の2倍
+ 答えを見る(こちらをクリック)
1.体の3分の1
カエルの舌は、自身の体の3分の1の長さと言われています。
そんなに長いものが口の中に納まっているのだから驚きです。
その舌で目にもとまらぬ速さで虫を捕食しています。
カエルの舌は、1秒間に4000メートルという驚異的な速さで獲物を捕らえます。これは、ジェット機の約6倍の速さと言われています。
第8問
6月の誕生石はパールですが、日本語では何と言うでしょうか?
1.鍾乳石
2.琥珀
3.真珠
+ 答えを見る(こちらをクリック)
3.真珠
パールは、『健康・富』の意味を持つ6月の誕生石です。
貝から採れる宝石の一種であるパール(真珠)は、生体がつくる鉱物であることから『生体鉱物(バイオミネラル)』とも呼ばれています。
天然物も存在はしますが、かなり希少価値が高い宝石です。
現在流通しているもののほとんどが養殖のパール(真珠)と言われています。
第9問
傘は使っているうちに水を弾きにくくなっていきます。
しかし、自宅でも簡単にできる方法で水を弾く力を復活させることができます。
それは一体なんでしょうか?
1.1ヶ月間閉じたまま放置する
2.ドライヤーで温風を当てる
3.氷水で冷やす
+ 答えを見る(こちらをクリック)
2.ドライヤーで温風を当てる
傘は『フッ素』を使って撥水加工(水を弾くための加工)されています。
新品の傘はフッ素が綺麗に縦に並んだ状態で、生地に水が染み込んでこないようになっています。
しかし、傘は使っていく中でフッ素の並びが乱れていき、水を弾く力が弱くなっていきます。
そこにドライヤーの温風を当てるとフッ素の並びが元のように綺麗になるため、また水を弾きやすくなります。
ただ、1つ注意点があり、この方法が使えるのは布製の傘のみです。ビニールの傘の場合は熱で変形してしまうため注意しましょう。
第10問
ジューンブライドの由来には、ある国の神様が関係しているとされています。
どこの国の神様でしょうか?
1.イタリア
2.日本
3.中国
+ 答えを見る(こちらをクリック)
1.イタリア
ジューンブライドは、ローマ神話が由来とされています。
ローマ神話では1月~6月まで、それぞれの月を守る神様がいるとされています。
ジューンブライドの由来は6月を守る神様である「女神ユノ」です。ユノは結婚や出産・育児の象徴とされ、女性や子供・家庭の守護神とも言われています。
このことから、6月に結婚する花嫁は幸せになれるという話が広まったとされています。
【高齢者向け】6月の雑学&豆知識クイズ問題【中編10問】


博士
前半10問はどうじゃったかのう?まだ物足りないという人は、次の10問にも挑戦してみるのじゃ!
第11問
梅雨時に天気予報を見ると、ズラリと傘マークが並んでいる光景を目にします。
実は天気予報で雨を表すマークとして傘を使うのはかなり少数派であり、他の多くの国は違うマークを使います。
天気予報の雨マークとして世界で最も多く使われているのはどんなものでしょうか?
1.レインコート
2.雨雲
3.カタツムリ
+ 答えを見る(こちらをクリック)
2.雨雲
天気予報で雨を表す場合、殆どの国は雨雲マークを使います。
傘マークを使うのは日本と韓国くらいなんだとか・・・。
第12問
ある動物が顔を洗うと雨が降ると言われています。
その動物はなんでしょうか?
1.ネコ
2.ネズミ
3.ウサギ
+ 答えを見る(こちらをクリック)
1.ネコ
昔から「ネコが顔を洗うと雨が降る」と言われています。
ネコのヒゲは空気の振動を敏感に感じ取れるセンサーの役割を持っています。
梅雨時は湿度が高くなるため、湿気によってネコのヒゲもハリが無くなってしまいます。
そうなるとネコは大切なセンサーの役割であるヒゲのハリを取り戻したいので、顔を洗うような行動を取ります。
第13問
トビウオは九州や日本海側では、人間の顔の部位のような別名で呼ばれています。
なんと呼ばれるでしょうか?
1.アゴ
2.ハナ
3.デコ
+ 答えを見る(こちらをクリック)
1.アゴ
トビウオが九州や日本海側の地域でアゴと呼ばれるようになった理由には諸説あります。
- あごが落ちるほど美味しいから
- 硬いので食べる時によく噛む(顎を使う)から
- トビウオを前から見ると顎が出ているから
トビウオから取れる出汁はアゴ出汁として親しまれており、お正月や祝いの席の料理にも使われます。
第14問
湿気が気になる梅雨時、身の回りにあるものを敷いておくだけで湿気対策ができます。
それは一体なんでしょうか?
1.アルミホイル
2.レジャーシート
3.新聞紙
+ 答えを見る(こちらをクリック)
3.新聞紙
新聞紙は紙の表面がデコボコしており、普通の紙よりも水分を吸収しやすい特徴があります。
そのため、湿気が気になるところに敷いておくだけでも除湿効果が期待できます。
第15問
6月が旬の野菜の1つにズッキーニがあります。
形がキュウリに似ていますが、実はキュウリの仲間ではありません。
では、どの野菜の仲間でしょうか?
1.トマト
2.ナス
3.カボチャ
+ 答えを見る(こちらをクリック)
3.カボチャ
ズッキーニは分類上、カボチャの仲間になります。
ズッキーニの花とカボチャの花を比べてみると、よく似ています。
そして、実もキュウリではなく、カボチャと同じようななり方をします。
第16問
6月はある病気の症状が強く出やすい時期でもあり、その病気に関する啓発や講演会が行われます。
その病気とは一体なんでしょうか?
1.うつ病
2.リウマチ
3.胃がん
+ 答えを見る(こちらをクリック)
2.リウマチ
6月は『リウマチ月間』です。
湿気が強く雨の多い時期はリウマチの痛みが強くなりやすいため、梅雨である6月がリウマチ月間に制定されています。
リウマチに関して正しい知識を普及・啓発するためのポスター掲示や講演会が行われています。
第17問
6月の第3日曜日は「父の日」です。
では、父の日発祥の国はどこでしょうか?
1.タイ
2.日本
3.アメリカ
+ 答えを見る(こちらをクリック)
3.アメリカ
アメリカのソノラ・スマート・ドットという女性が、1909年(明治42年)に牧師教会へ「母の日だけではなく、父親へ感謝する日も作ってほしい」と嘆願しました。
そして、1910年(明治43年)6月19日に初めて父の日の式典が開催されました。しかし、この時点では先に成立していた母の日ほど認知されていませんでした。
1916年(明治49年)の父の日の式典で、第29代アメリカ大統領ウッドロー・ウィルソンが演説を行ったことをきっかけに広まっていきました。
ちなみに、日本に父の日が伝わったのは1950年代と言われていますが、現代のように一般的に知られるようになったのは1980年代と言われています。
第18問
毎年5月31日~6月6日は、国民の健康のためにあることを呼び掛ける週になっています。
なにを呼び掛けているでしょうか?
1.禁煙
2.禁酒
3.ダイエット
+ 答えを見る(こちらをクリック)
1.禁煙
毎年5月31日~6月6日は、『禁煙週間』です。
タバコの煙には約5300種類の化学物質が含まれており、そのうち約70種類は発がん物質です。
タバコは依存症や、吸った本人だけではなく周りの人の健康にも被害を及ぼす受動喫煙の問題もあります。
毎年5月31日は、世界保健機関(WHO)が定めた『世界禁煙デー』として喫煙を控えることを呼び掛ける日です。
そのため、日本でも、5月31日から始まる1週間を『禁煙週間』としてタバコと健康に関しての理解を深めるための活動が行われる週となりました。
第19問
『傘』と『笠』。
読みは同じ漢字ですが、どのように使い分けるでしょうか?
1.『傘』はさすもの、『笠』は被るもの
2.『傘』は海外製、『笠』は国産
3.『傘』は明治時代以降に作られたもの、『笠』は江戸時代までに作られたもの
+ 答えを見る(こちらをクリック)
1.『傘』はさすもの、『笠』は被るもの
『傘』と『笠』はどちらも雨や日差しを遮るための道具ですが、ちゃんと使い分けされる漢字です。
『傘』は私たちが日頃使っている一般的なもので、使う時は手に持って『さす』もの。一方、『笠』は帽子のように『被る』ものです。
明治時代以降には『傘』や帽子が普及したことで、少しずつ使われる機会が少なくなっていきました。昔話の『かさじぞう』にはこの『笠』の方が登場しています。
第20問
6月は梅雨で雨が多く降るにも関わらず、「水無月(みなづき)」と言います。
それは一体なぜでしょうか?
1.キレイな飲み水が不足する時期だから
2.水筒の水があっという間に無くなるほど暑いから
3.『無』が『ない』以外の意味で使われている
+ 答えを見る(こちらをクリック)
3.『無』が『ない』以外の意味で使われている
水無月の『無』は『ない』という意味ではなく、連体助詞である『の』の意味を持っています。
つまり、水無月は『水の月』という意味になります。
田んぼに水を張る時期であったため、水無月の他にも、水張月(みずはりづき)などとも呼ばれていました。
【高齢者向け】6月の雑学&豆知識クイズ問題【後編10問】


博士
中編10問はどうじゃったかのう?「まだまだ物足りない!」という人は、次の10問にも挑戦してみるのじゃ!
第21問
カタツムリの歯はどれくらいあるでしょうか?
1.約10~20本
2.約100~200本
3.約10000~20000本
+ 答えを見る(こちらをクリック)
3.約10000~20000本
カタツムリには、約10000~20000本もの歯があります。
人間の歯と違ってヤスリ状になっており、その歯を活用してコンクリートに含まれるカルシウムを食べています。
第22問
和傘と洋傘、骨の数が多いのはどちらでしょうか?
1.和傘
2.洋傘
3.骨の数は同じ
+ 答えを見る(こちらをクリック)
1.和傘
洋傘は骨の数が通常8本であるのに対し、和傘の骨の数は30本~70本と非常に多くなっています。
洋傘は骨の針金の張力で生地を内側から押し上げて開く仕組みであるのに対し、和傘は細く割った多くの竹骨で和紙を支えるようにして開く仕組みです。
この仕組みの違いが骨の数に現れています。
第23問
世界一傘の年間消費量が多い国はどこでしょうか?
1.日本
2.アメリカ
3.ブラジル
+ 答えを見る(こちらをクリック)
1.日本
日本の洋傘の消費量は世界一であり、年間1億2000万本程度と言われています。
これは日本国民ほぼ全員が1年に1本傘を買っているようなものです。
日本ではコンビニなどで気軽にビニール傘を買うことができ、それがほぼ使い捨てのようになっていることも傘の消費量が多い理由です。
第24問
梅雨時に旬を迎える魚はどれでしょうか?
1.カワハギ
2.サンマ
3.イワシ
+ 答えを見る(こちらをクリック)
3.イワシ
梅雨の時期に獲れるマイワシのことを「梅雨イワシ」と呼びます。
マイワシの旬は6〜7月であり、この時期のマイワシは産卵前で脂が乗っています。
第25問
梅雨時に行われる「梅仕事」とはなんでしょうか?
1.梅の木の剪定をすること
2.梅干しや梅酒を作ること
3.梅を出荷すること
+ 答えを見る(こちらをクリック)
2.梅干しや梅酒を作ること
「梅仕事」とは、梅が旬を迎える時期に梅干しや梅酒などを作ることを指します。
梅が収穫できるのは、梅雨の季節に当たる6月頃です。
第26問
衣替えはどの国から日本に伝わった習慣でしょうか?
1.中国
2.モンゴル
3.ポルトガル
+ 答えを見る(こちらをクリック)
1.中国
衣替えは、中国の宮廷で旧暦の4月1日と10月1日に季節に合わせて服を入れ替えていたことから始まった習慣です
日本に伝わったのは平安時代であり、江戸時代までには四季に合わせて服を入れ替える習慣が根付きました。
第27問
関西地方には夏至にあるものを食べる風習があります。
それはなんでしょうか?
1.そうめん
2.ふきのとう
3.タコ
+ 答えを見る(こちらをクリック)
3.タコ
関西地方では、夏至にタコを食べる風習があります。
「稲の根がタコの足のように四方八方にしっかりと根付くように」という願いが込められています。
第28問
夏至に「ミッドサマー」というお祭りが開かれる国はどこでしょうか?
1.インド
2.スウェーデン
3.オーストラリア
+ 答えを見る(こちらをクリック)
2.スウェーデン
「ミッドサマー」は、クリスマスと並ぶスウェーデンで最も重要な行事の1つです。
元々はキリスト教に由来しており、洗礼者ヨハネをお祝いする行事であるとされていました。
現在では、「長い冬が終わり夏が訪れたことを祝うお祭り」という認識が一般的だそうです。
クリスマスは家族と過ごす人が多数派であるのに対し、ミッドサマーは友人と一緒に過ごす人も多いようです。
第29問
6月の満月をなんと呼ぶでしょうか?
1.ストロベリームーン
2.アップルムーン
3.パイナップルムーン
+ 答えを見る(こちらをクリック)
1.ストロベリームーン
6月の満月は、ストロベリームーンと呼ばれます。
アメリカ先住民の間では、6月に苺の収穫をすることがその名の由来です。
また、「ストロベリームーンを好きな人と一緒に見ると結ばれる」とも言われています。
第30問
沖縄県が制定した「慰霊の日」は6月何日でしょうか?
1.6月1日
2.6月12日
3.6月23日
+ 答えを見る(こちらをクリック)
3.6月23日
太平洋戦争末期の1945年(昭和20年)6月23日、沖縄で県民を巻き込んだ地上戦が終結しました。
そのことから沖縄県では、毎年6月23日を沖縄戦の戦没者の霊を慰め平和を祈る「慰霊の日」として県の条例で記念日に定めています。

博士
今回のクイズ問題は以上じゃ!君は何問解けたかな?
このサイトではいろんな脳トレクイズを紹介しているから、ぜひ他のクイズにも挑戦してみるのじゃ!