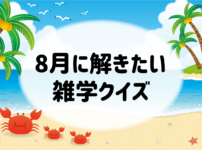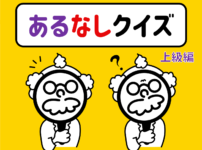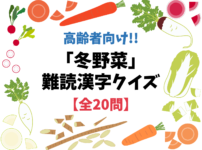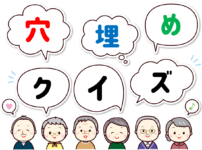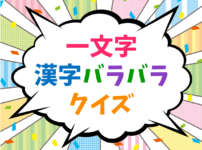目次
【都道府県スリーヒントクイズ】高齢者向け!簡単・盛り上がる高齢者向け問題【前編10問】
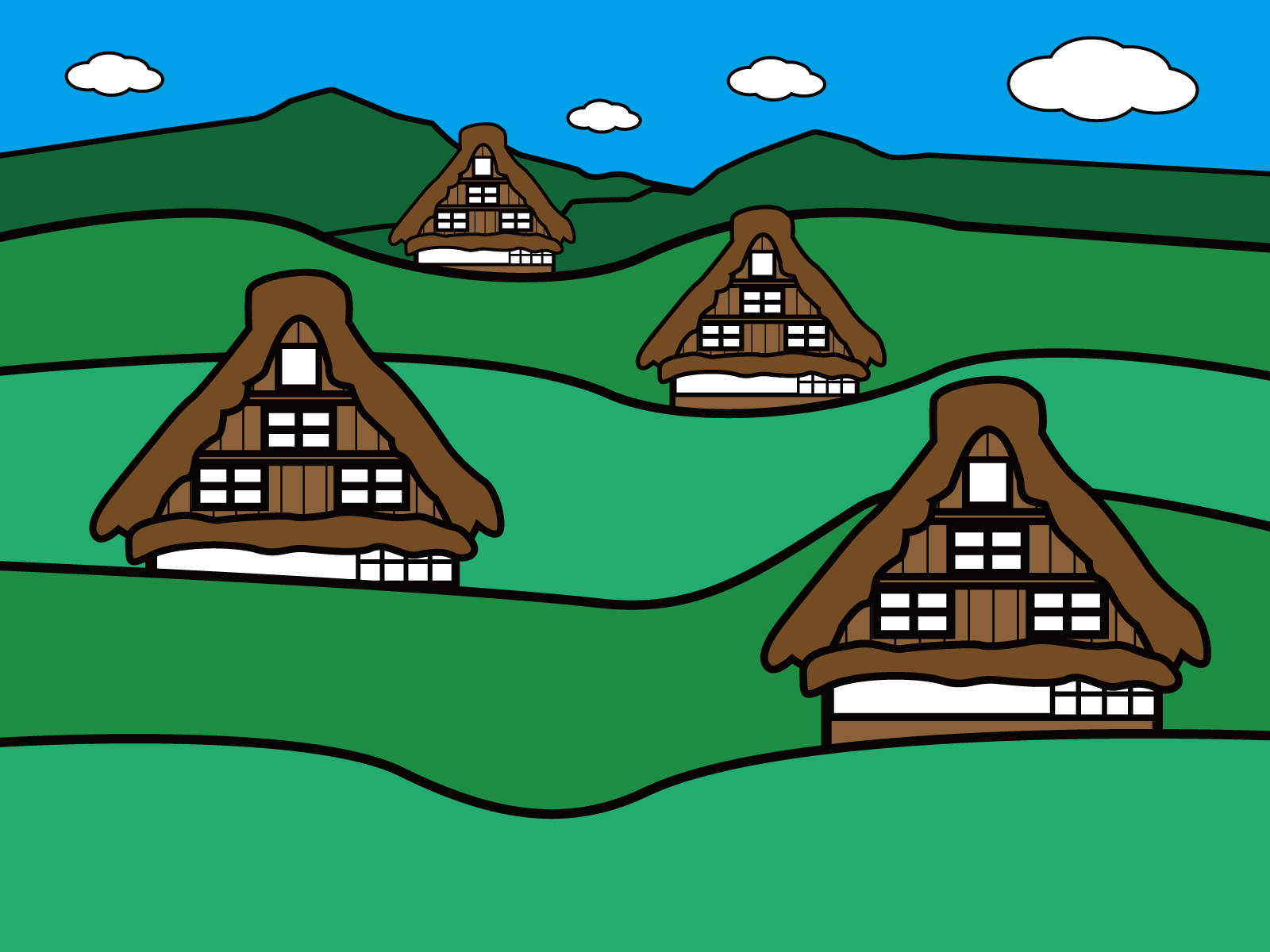

第1問
- リンゴ
- 津軽弁
- ねぶた祭り
+ 答えを見る(こちらをクリック)
答え:青森県
青森県はリンゴの生産量日本一です。1878年(明治11年)に植えられた国内最古のリンゴの木が今も残っています。
津軽弁は、青森県津軽地方の方言で、全国でも難解な方言とも言われています。同じ青森県内であっても津軽弁を使わない地域の方だと、津軽弁が全然分からないことも珍しくないのだとか。
ねぶた祭りは、青森県の有名なお祭りです。武士などを描いた大きな燈籠を台に乗せて、街中を練り歩くもので多くの観光客が訪れます。また、県内でも「ねぶた」と呼ぶ地域と、「ねぷた」と呼ぶ地域があります。
第2問
- 舞妓さん
- 八つ橋
- 清水寺
+ 答えを見る(こちらをクリック)
答え:京都府
「芸妓」という、宴席で唄や踊りや三味線などの芸で興を添えることを仕事とする女性がおり、「舞妓」はその見習の段階の若い女性を指します。江戸時代、街道を通る旅人にお茶を振る舞った茶屋の女性たちが起源と言われています。
八つ橋は京都のお土産の定番です。生ではない八つ橋は煎餅であり、江戸時代から親しまれています。生八つ橋は1960年(昭和35年)に誕生しました。
清水寺は京都の有名な観光地の1つであり、奈良時代に建てられたと言われています。
「清水の舞台」とも呼ばれる清水寺の現在の本堂は、江戸時代に急増した参拝客が安全に参拝できるようにするために増築されたものです。崖の上に建っていたので増築するスペースが無かったため、崖の上にせり出す形での増築になりました。
第3問
- きし麵
- しゃちほこ
- 味噌カツ
+ 答えを見る(こちらをクリック)
答え:愛知県
きし麵は、幅が広くて薄い麺です。その起源ははっきりしていませんが、江戸時代の記録には既にその存在が記されています。その形状から茹で時間が短く、表面が滑らかな食感を楽しめる反面、うどんよりもコシが弱めです。
しゃちほこは、名古屋城の天守閣にある物が有名です。体は魚で頭は虎という空想上の生き物であり、火事から城を守るまじないの意味がありました。
味噌カツは、とんかつに味噌ダレをかけた名古屋名物であり、詳細は不明ですが昭和40年頃には飲食店のメニューにあったようです。
第4問
- 伊藤博文
- 錦帯橋
- フグ
+ 答えを見る(こちらをクリック)
答え:山口県
山口県は伊藤博文を始めとした歴代内閣総理大臣の輩出数が日本一であり、2020年(令和2年)時点で8人の総理大臣を輩出しました。
錦帯橋は、日本三名橋や日本三大奇橋の1つに数えられる橋であり、5連のアーチ構造という世界でも珍しい形をしています。
山口県下関市は、フグの水揚げ量が日本一です。フグによる死者が多かったことから、かつて豊臣秀吉がフグ禁止令を出していました。そんなフグを解禁させたのは伊藤博文であると言われています。
第5問
- 輪島塗
- 金箔
- 兼六園
+ 答えを見る(こちらをクリック)
答え:石川県
石川県輪島市で作られている漆器が、「輪島塗」です。現存する最古の輪島塗は、輪島市河井町にある重蔵神社の朱塗扉で、1524年に作られたものであると言われています。
金箔は国内で生産される物の、99%が石川県金沢市で作られています。金箔は食用の物もあり、体内で吸収されることがない安全な物質で、食品添加物と認められています。
兼六園は、日本三名園の1つです。兼六園には、日本初の西洋式銅像(日本武尊像)があります。この銅像にはヒ素が通常の銅像よりも多く含まれており、そのためか何故か鳥が寄り付きません(何故ヒ素が多いと鳥が寄り付かないのかまでは不明)。
第6問
- 刃物
- 関ヶ原の戦い
- 合掌造り
+ 答えを見る(こちらをクリック)
答え:岐阜県
岐阜県は刃物の生産量が日本一であり、その多くが関市で作られています。質の良い刃物は国内外問わず人気があり、特に包丁は一流のシェフの中にも関市の物を好んで使う人もいる程です。
岐阜県関ケ原町は、関ヶ原の戦いが行われた場所として有名です。徳川家康率いる東軍と、石田三成率いる西軍が争った合戦ですが、西軍の小早川秀秋の軍勢が東軍に寝返ったこともあり僅か6時間で東軍の勝利で終わったと言われています。
白川郷の合掌造りは世界遺産にもなっています。急勾配な屋根の形が合掌した時の手の形に似ているため「合掌造り」と呼ばれます。このような形になった理由は、雪が屋根から自然に落ちる作りにすることで家が雪で潰れるのを防ぐためです。
第7問
- 信楽焼(しがらやき)
- 忍者
- 琵琶湖
+ 答えを見る(こちらをクリック)
答え:滋賀県
信楽焼は、甲賀市信楽町を中心とした地域で造られている陶器です。お店の前などにも置かれている陶器の狸の置物で有名です。
1951年(昭和26年)、昭和天皇の信楽行幸の際、沢山の信楽焼のたぬきに日の丸の小旗を持たせ沿道に建たせたのをご覧になった昭和天皇が感動したことから、信楽焼の狸が有名になりました。
滋賀県は甲賀流忍者も有名です。フィクションの中では伊賀流と宿敵のように描かれることもあります。実際に争っていた時期もあったとされていますが、基本的には良好な関係だったと言われています。
滋賀県と言えば琵琶湖を連想する方も多く、県面積の6分の1を占めています。また、琵琶湖には世界でも琵琶湖にしか存在しない固有種が生息することでも知られています。
第8問
- トルコライス
- オランダ坂
- 眼鏡橋
+ 答えを見る(こちらをクリック)
答え:長崎県
トルコライスは、とんかつ、ピラフ、スパゲッティが1つの皿に盛られた長崎のご当地グルメです。トルコと名がついてはいますが、トルコは一切関係がありません。そもそもトルコはイスラム教の国であるため、豚肉を食べません。名前の由来は、フランス語の「トリコロール(三色という意味)」が訛ってトルコになったという説がありますが、詳細は分かっていません。
オランダ坂とは、「誠孝院前の坂」、「活水坂」、「活水学院下の坂」の三つの坂の総称です。長崎県では開国後、外国人はオランダ人もそうでない人も全てひっくるめて「オランダさん」と呼んでおり、当時「オランダさんが通る坂」という意味で居留地にある坂はすべてオランダ坂と呼んでいたと言われています。
眼鏡橋は、1634年に架けられた橋であり、当時はまだ琉球王国だった沖縄の天女橋を除けば、日本初の石造りアーチ橋と言われており、国の重要文化財に指定されています。
1982年(昭和57年)の長崎大水害では眼鏡橋を含む中島川の九つの石橋が被害に遭い、そのほとんどが流されてしまった中、眼鏡橋は半分程度損壊する大きなダメージを受けましたが何とか持ちこたえました。
第9問
- 海女さん
- 真珠
- なばな
+ 答えを見る(こちらをクリック)
答え:三重県
三重県は海女さんが最も多い県です。2010年時点の全国調査の数値ではありますが、全国に2160人の海女さんがいることが判明しました。その中で最も多い県は三重県で、973人。次いで石川県197人、千葉県158人…と全国人数の半数近くが三重県の海女さんということが分かります。
三重県は真珠養殖の発祥の地です。1893年(明治26年)に御木本幸吉翁が実験中のアコヤ貝より半円真珠5個を発見し、アコヤ貝による養殖法を発明したのが始まりです。
なばなは、主にアブラナの芯の部分を若葉とともに摘み取ったものであり、三重県はその生産量が日本一です。また、三重県には名産品のなばなから名を取った「なばなの里」という植物園があり、季節の花やイルミネーションを楽しむことができます。
第10問
- 気球
- シシリアンライス
- 小城羊羹
+ 答えを見る(こちらをクリック)
答え:佐賀県
佐賀県では、アジア最大の熱気球の大会が開催されています。その名も「佐賀インターナショナルバルーンフェスタ」です。1978年(昭和53年)に福岡県甘木市で熱気球大会「バルーンフェスタ・イン九州」が開催されたのが始まりであり、1980年(昭和55年)より福岡空港の離着陸圏内に影響することから会場が佐賀に移され、現在に至ります。
シシリアンライスは、1枚の皿に温かいライスを敷き、その上に炒めたお肉と生野菜を盛り合わせ、マヨネーズをかけたものが基本となる佐賀のご当地グルメです。起源や名称の由来は分かっていませんが、昭和50年頃に県内のとある喫茶店で提供されたのが始まりと言われています。
小城羊羹とは、佐賀県で作られている羊羹の1つです。外側は砂糖のシャリシャリした食感があり、中は柔らかいという特徴があり人気を集めています。時間の経過で外側のシャリシャリ感が増しますが、羊羹ですのであまり長期間の日持ちはしないため注意しましょう。
【都道府県スリーヒントクイズ】高齢者向け!簡単・盛り上がる高齢者向け問題【中編10問】


第11問
- 雷門
- 皇居
- スカイツリー
+ 答えを見る(こちらをクリック)
答え:東京都
雷門は、浅草にある有名な観光スポットの1つです。雷門と言えば、多くの方が思い浮かべる大きな提灯はなんと高さ3.9メートルもあります。正式名称は「風雷神門」であり、提灯の「雷門」と書かれた面の反対側には「風雷神門」と書かれています。
皇居は、明治維新までは京都にありましたが、1869年(明治2年)に東京に移りました。皇居と呼ばれるようになったのは1948年(昭和23年)からであり、それ以前は皇城、宮城といった呼び名が使われていました。
東京スカイツリーは、2012年(平成24年)に完成した東京の新たなシンボルであり、634mと世界一の高さを誇っています。ギネス認定もされています。
第12問
- おでん
- うなぎ
- お茶
+ 答えを見る(こちらをクリック)
答え:静岡県
静岡おでんは、普通のおでんにはない特徴があります。「スープが黒い」、「具に串が刺してある」、「黒はんぺんが入っている」、「青海苔・だし粉をかける」といったのがその特徴であり、なんと駄菓子屋さんでも売っている身近な存在です。
静岡県浜松市の浜名湖は、実はうなぎの養殖の発祥の地であり、浜名湖のうなぎと言えば人気のあるブランドとなっています。
静岡県と言えば、言わずと知れたお茶の産地であり国内生産の約4割を占めています。また、静岡県の学校にはお茶が出る蛇口が設置されているところがあります。
第13問
- 串カツ
- お好み焼き
- 通天閣
+ 答えを見る(こちらをクリック)
答え:大阪府
大阪の串カツと言えば提供された串カツを、容器に入ったソースにつけていただくスタイルのため衛生面の関係から「二度づけ厳禁」で有名です。ソースを追加したい場合は、キャベツですくってかけて食べます。
大阪と言えばお好み焼きが有名です。広島のお好み焼きは生地の上に具を乗せて焼くのに対し、大阪のお好み焼きは生地と具を混ぜた状態で焼くという違いがあります。
通天閣と言えば、大阪のシンボルとして有名です。実は現代の通天閣は2代目であり、1956年(昭和31年)に再建されたものです。初代通天閣は戦時中に強度が不安定になったことから解体されています。
第14問
- 白くまアイス
- 黒豚
- 桜島
+ 答えを見る(こちらをクリック)
答え:鹿児島県
白くまは、かき氷に練乳をかけて、フルーツや小豆餡を盛り付けたデザートです。その名前の由来は諸説あり、はっきりしたことは分かっていませんが今ではコンビニなどでも販売され全国に知られる存在となっています。
鹿児島県は養豚が盛んであり、豚の飼育数は日本一です。鹿児島と言えば上質な肉で知られる黒豚が有名です。鹿児島の黒豚は、約400年前に琉球から鹿児島に移入されたのが始まりと言われています。
鹿児島県のシンボルとも言われる桜島は、以前はその名の通り1つの島でしたが、1914年(大正3年)の大正噴火で流れた溶岩によって海峡が埋め立てられたことで、大隅半島と陸続きになっています。
第15問
- 蜃気楼
- お薬
- 黒部ダム
+ 答えを見る(こちらをクリック)
答え:富山県
富山県魚津は江戸時代以前から蜃気楼の名所として知られています。蜃気楼は大気中で光が屈折し虚像が見える自然現象で、気温や風などの条件が整わないと発生せず、条件が少し変わるだけで蜃気楼にも変化が見られるため、同じ蜃気楼は二度と見ることができないと言われます。
富山県は医薬品の生産が盛んな県でもあります。1639年に加賀藩から分藩した富山藩は財政難に苦しめられていました。そこで、本家の加賀藩に依存しない経済基盤をつくるために産業を奨励し、その一つに製薬があったことが始まりと言われています。
黒部ダムは、えん堤の高さ186mは日本一を誇る観光名所としても有名なダムです。観光放水で流れ出る水量は毎秒10t以上という圧巻の数値であり、運が良ければ虹がかかる程です。
第16問
- 相撲発祥の地
- しじみ
- 出雲大社
+ 答えを見る(こちらをクリック)
答え:島根県
島根県は、国譲り神話や野見宿祢の伝承などから相撲発祥の地であると考えられています。そのためか相撲との縁も深く、江戸時代に松江藩は非常に強い力士を何人も抱えていたとの記録も残っています。
島根県にある宍道湖は海水と淡水が混ざり合う汽水湖で、国内の漁獲高日本一を誇るヤマトシジミが有名です。その肉厚な実はみそ汁や佃煮など様々な形で愛されています。
島根県は、縁結びの神として名高い大国主神が祀られる出雲大社も有名です。神社の参拝に関しては語呂合わせで「いくらが良い」といった話はよく耳にしますが、出雲大社は公式「ホームページにて「祈りの心は金額や語呂合わせに左右されるものではない」といった旨の回答をしています。
第17問
- パンダ
- 那智の滝
- みかん
+ 答えを見る(こちらをクリック)
答え:和歌山県
和歌山県にあるアドベンチャーワールドは、これまでに17頭のパンダの繁殖実績があります。この記録は中国以外の施設では世界一です。
那智山中には約60の滝があり、そのうち瀧篭修行で使われた48の滝の総称が「那智の滝」です。しかし、一般的に「那智の滝」として知られるのがその中の1つで「一の滝」と呼ばれる滝です。落差133メートルと、一段滝としては日本の落差を誇ります。
和歌山県はミカンの生産量が日本一です。そんなミカンは食べて美味しいだけではなく、フルーツ魚という果物の皮などをエサに混ぜた魚を育てるためにも使われます。フルーツ魚は、魚の生臭さが抑えられ、苦手な人でも食べやすくなります。
第18問
- ジーンズ
- ままかり
- 晴れの国
+ 答えを見る(こちらをクリック)
答え:岡山県
岡山県はジーンズの生産量が日本一であり、国産ジーンズ発祥の地でもあります。岡山県は江戸時代に綿花栽培が始まってから繊維業が盛んであり、学生服の生産量も岡山県が日本一で「トンボ」などの大手メーカーも岡山県にあります。
ままかりはニシンの仲間の魚です。西日本では「ままかり」、東日本では「さっぱ」と呼ばれる傾向があります。岡山県では酢漬けや塩焼きにしたものが郷土料理として親しまれてきました。「ままかり」の名の由来は、「この魚のあまりの美味しさに、まま(飯)を食べ尽くしたので隣からまま(飯)を借りてでも食べたい」という美味しさを表現する言葉から来ているとされています。
岡山県は「晴れの国」と言われています。しかし、晴れの日が日本一多いわけではありません。気象庁の定義では「雲の量が2割以上8割以下」が晴れ、「雲の量が1割以下」が快晴となっています。しかし、岡山県は「降水量1mm以下の日が最も多い県」です。雨が少なく温暖で、自然災害の少ない県ということなどから「晴れの国」と言われます。
第19問
- レモン牛乳
- いろは坂
- 足尾銅山
+ 答えを見る(こちらをクリック)
答え:栃木県
レモン牛乳は、栃木で愛される乳飲料です。「関東牛乳」が第二次世界大戦後間もない頃に「関東レモン牛乳」の名前で発売したのが始まりです。栃木県産の生乳に砂糖やレモン香料などを加えたレモン色をした飲料ではありますが、実際にレモン果汁を入れると酸によって牛乳が固まってしまうため果汁そのものは入っていません。
いろは坂は、日光市街と中禅寺湖・奥日光を結ぶ観光道路です。下り専用の「第一いろは坂」と上り専用の「第二いろは坂」があり、2つの坂を合計すると48か所もの急カーブがあることから「いろは48文字」に例えて、いろは坂という名になりました。
足尾銅山はかつて、「日本一の鉱都」と呼ばれ栄えていました。閉山後に坑内の一部が開放され、トロッコ電車乗って坑道を観ることができます。人形によって当時の過酷な作業の様子が再現されています。
第20問
- ガマの油
- ヤンキーが多い
- 竜神大吊橋
+ 答えを見る(こちらをクリック)
答え:茨城県
ガマの油は、元々は江戸時代に傷薬として用いられていた軟膏です。中禅寺の住職であった光誉上人の陣中薬の効果が評判になったことで広まったとされており、名前の由来は光誉上人の顔がガマガエルに似ていたからというものなどがあります。実際にガマガエルの油(分泌液)は入っていなかったと言われています。現在もワセリンを主成分とする軟膏として売られています
茨城県はヤンキーが多い県とも言われています。実際に2019年(令和元年)8月14日~2020年(令和2年)12月8日にかけて行われた「ヤンキーが多そうな県といえば?」というアンケートで、2014年(平成26年)に行われた物に続き1位を獲得しています。茨城県は直線道路の総延長が全国2位であり、広大でまっすぐな道が多いことから暴走族が多くなる傾向があると言われています。
茨城県にある竜神ダムの上に架けられた竜神大吊橋は、長さは375mと歩行者専用の橋としては日本最大級の長さを誇ります。厳しい自然条件にも耐えるよう安全性に十分な注意が払われており、一度に3,500人もの人が渡っても大丈夫なように工夫が凝らされています。
【都道府県スリーヒントクイズ】高齢者向け!簡単・盛り上がる高齢者向け問題【後編10問】


第21問
- ラベンダー畑
- 白い恋人
- 雪まつり
+ 答えを見る(こちらをクリック)
答え:北海道
例年6月下旬ごろより早咲の品種が色づき始め、7月中旬~下旬ごろに見頃のピークを迎えます。ラベンダー畑で有名な中富良野町の「ファーム富田」にもこの時期に行けば広大なラベンダー畑を楽しむことができます。
北海道のお土産と言えば「白い恋人」が有名です。札幌市にある「白い恋人パーク」では、工場見学やお菓子作り体験などを楽しむことができます。
さっぽろ雪まつりは、北海道札幌市の大通公園などで開催される雪と氷の祭典です。国内や海外から200万人もの観光客が訪れる大きなイベントです。夜は午後10時まで会場がライトアップされるため、昼とはまた違った姿を見ることができるでしょう。
第22問
- サンゴ礁
- サーターアンダギー
- 美ら海水族館
+ 答えを見る(こちらをクリック)
答え:沖縄県
日本には約400種のサンゴが生息しており、特に沖縄の海では色鮮やかなサンゴの姿が多く見られます。サンゴ礁にはたくさんの生き物が集まって来るため、ダイビング体験をすれば豊かな生態系を見ることができるでしょう。
サーターアンダーギーは、沖縄県の揚げ菓子の一種であり「油で揚げたもの」という意味です。縁起の良い菓子とされており、結婚式など祝い事でも振る舞われることがあるそうです。
美ら海水族館は、沖縄県にある有名な水族館です。世界で初めて長期飼育に成功したジンベエザメやナンヨウマンタなどが人気の展示です。水族館内には水槽を眺めながらくつろげるカフェもあります。
第23問
- 乳頭温泉
- いぶりがっこ
- なまはげ
+ 答えを見る(こちらをクリック)
答え:秋田県
乳頭温泉郷は、秋田県仙北市・十和田八幡平国立公園内乳頭山の山麓に点在する温泉の総称です。十種類以上の源泉があるため、様々な温泉を楽しむことができます。
いぶりがっこは、燻製干しのたくあん漬けです。現在では全国的に有名ですが、その発祥は秋田県です。秋田県の気候は、たくあん作りのための天日干し大根が十分乾燥しないまま氷点下になるため、家の囲炉裏の上で大根を干していたところ誕生したのが「いぶりがっこ」です。
なまはげとは、男鹿の山々に住む神の使いです。人の怠け心を戒めるだけでなく、厄災を払って豊作や豊漁をもたらしてくれる存在であるとされています。見た目は鬼のように見えて怖いかもしれませんが、とてもありがたい存在だと言えるでしょう。
第24問
- 異人館
- 有馬温泉
- 甲子園
+ 答えを見る(こちらをクリック)
答え:兵庫県
異人館とは、幕末・明治時代以降に欧米人が居住するために住宅として建設した西洋館のことです。兵庫県神戸市の北野町山本通には当時の住宅が多数残っており、「北野異人館街」として知られています。
有馬温泉は、兵庫県神戸市北区有馬町にある温泉です。褐色の名物湯「金泉」と、無色透明な「銀泉」の異なる泉質を持つ温泉を楽しむことができます。なんと、豊臣秀吉も湯治に訪れていたと言われています。
阪神甲子園球場は兵庫県西宮市甲子園町にある野球場であり、「甲子園球場」という通称でも親しまれています。現存する野球場としては国内最古であり、収容人数は現在でも国内最大の規模を誇っています。
第25問
- じゃこ天
- ポンジュース
- 道後温泉
+ 答えを見る(こちらをクリック)
答え:愛媛県
じゃこ天は、愛媛県の郷土料理の1つです。小魚の身だけでなく皮や骨もすり潰し、小麦粉・卵・塩を加え堅めに混ぜて小判のような形に整え油で揚げて作ります。骨ごと使っているためカルシウムなども含まれており栄養満点です。
ポンジュースは、愛媛県で誕生した有名なみかんジュースです。その名前は日本一のジュースになるようにとの願いを込めてつけられたものであり、「日本(ニッポン)一」の「ポン」からきています。
道後温泉は「日本書記」にも登場しており日本最古の温泉であるとされています。夏目漱石の小説「坊ちゃん」にも描かれているほか、ジブリ映画「千と千尋の神隠し」も道後温泉がモデルになっているそうです。
第26問
- 桂浜
- 土佐犬
- カツオのたたき
+ 答えを見る(こちらをクリック)
答え:高知県
桂浜は、高知県を代表する観光名所の1つです。古くから月の名所として知られており、高知の唄「よさこい節」の歌詞にもその情景が残されています。
土佐犬と言えば、「闘犬」というイメージがあります。闘犬は、鎌倉時代や室町時代の頃から行われていたと言われています。幕末の頃には、藩士の士気を高めるために土佐藩で闘犬が盛んに行われるようになったと言われています。
カツオのたたきは現在では全国的に食べられている料理ですが、元々は高知県の郷土料理です。鰹を節に切り、表面のみを炙って冷やして切り、薬味とタレをかけて食べます。漁師が船上でまかないとして食べていたものが広まったという説があります。また、保存技術のない時代に船上で鮮度が落ちたカツオを食べるために広まった調理法だとも言われています。
第27問
- スパリゾートハワイアンズ
- 喜多方ラーメン
- 赤べこ
+ 答えを見る(こちらをクリック)
答え:福島県
スパリゾートハワイアンズは、福島県いわき市にある大型レジャー施設です。「温泉の地熱と豊富な湯量を利用すれば、東北の地でも一年間温暖な空間が創出できるのではないか」という発想から作られたそうです。
喜多方ラーメンは、福島県喜多方市発祥のご当地ラーメンです。麺は「平打ち熟成多加水麺」と呼ばれるものが使われます。一般的には麺の幅が約4mmの太麺であり、水分を多く含ませじっくりねかせて作ります。コシと独特の縮れが特徴的な麺です。
赤べこは、福島県会津地方の張子の郷土玩具です。「べこ」とは東北地方の方言で「牛」という意味です。「平安時代に蔓延した疫病を赤い牛が払った」という伝承が由来であり、可愛らしい見た目でありながら厄除けの意味が込められています。
第28問
- 花笠まつり
- 芋煮会
- さくらんぼ
+ 答えを見る(こちらをクリック)
答え:山形県
山形市で毎年8月5日から7日まで開催される「山形花笠まつり」は、約1万4千人の踊り手と約100万人の観客が集まる夏祭りです。大正時代に山形県北東部の尾花沢市の戸倉湖沿いに堤防を建設していた労働者によって作られたと言われています。
芋煮会とは、山形県や宮城県など東北地方各地で行われる秋の行事です。河川敷などに集まり、サトイモを使った鍋料理を作って食べる行事です。山形県山形市で毎年行われている「日本一の芋煮会フェスティバル」は、6m以上の巨大な鍋を使った光景がニュースでも流れておりとても印象的です。
山形県はサクランボの生産量が日本一であり、全国の約7割を占めています。山形県でサクランボ栽培が始まったのは明治時代初期の頃とされています。サクランボの実は強い雨に打たれると割れてしまう雨に弱い作物であるため、山に囲まれ空梅雨になることが多い山形の環境が栽培に非常に適していたと言えます。
第29問
- 三方五湖
- 東尋坊
- 越前ガニ
+ 答えを見る(こちらをクリック)
答え:福井県
三方五湖は、福井県美浜町と若狭町にまたがる三方湖・水月湖・菅湖・久々子湖・日向湖の5つの湖の総称です。5つの湖は水質や水深が違っており、全て濃さの違う青色に見えることから「五色の湖」と呼ばれています。
東尋坊は、越前加賀海岸国定公園にある国の天然記念物です。巨大な柱状の岩が織り成す約1kmに渡る海岸線に広がる景観が特徴です。サスペンスドラマのロケ地に使われることでも有名です。
越前ガニとは、福井県で水揚げされるオスのズワイガニのことです。メスのズワイガニは、「せいこガニ」と呼ばれています。越前におけるズワイガニ漁の歴史は国内で最も古いと言われており、室町時代の記録には既に「越前蟹」という表記で登場しています。
第30問
- 青葉城
- ずんだ餅
- 松島
+ 答えを見る(こちらをクリック)
答え:宮城県
青葉城とは、青葉山に建造されたことから付けられた「仙台城」の雅称です。残念ながら城は残っておらず現在は城跡となっていますが、青葉城資料展示館ではコンピューターグラフィックスによる青葉城復元映像などを見ることができます。
ずんだ餅は、すりつぶした枝豆を餡に用いる宮城県の代表的な餅菓子です。名前の由来には諸説あり、そのうちの1つには「伊達政宗公が陣太刀の柄で枝豆を砕いた」という説もあります。
松島町は、日本三景の1つに数えられています。「四大観」と呼ばれる絶景スポットからは、それぞれ違った魅力のある景気を楽しむことができます。

このサイトではいろんな脳トレクイズを紹介しているから、ぜひ他のクイズにも挑戦してみるのじゃ!