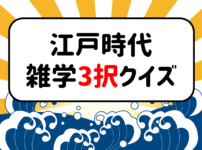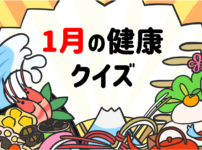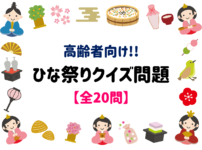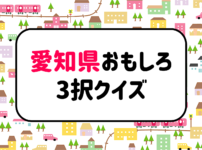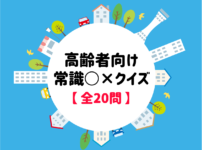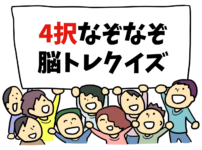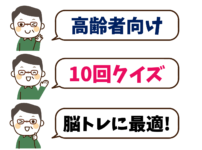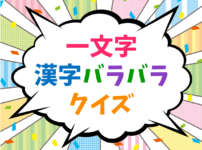博士
今回は昭和に関する三択クイズ問題を紹介するぞ!昔を思い出しながら解いてみるのじゃ!
【高齢者向け】昭和に関する三択クイズ問題【前編10問】


博士
まずは10問出題するぞぉ!3つの選択肢を出すから正解だと思うものを一つ選ぶのじゃ。脳の良い刺激になるぞぉ。
第1問
昭和40年頃の理髪店の料金はいくらだったでしょうか?
1.560円
2.350円
3.1000円
+ 答えを見る(こちらをクリック)
2.350円
今では考えられないような値段です。とは言え、当時と現代では物価の違いもあるので、現代の350円と全く同じかと言えばそうではありません。
令和元年時点の物価が昭和40年の約2.1倍とされており、単純計算で言えばだいたい735円ということになります。
現代の物価に換算して考えると、1000円カットのお店より少し安いくらいになります。
第2問
昭和40年代、コカ・コーラの瓶をお店に返すと「ある物」が貰えました。それは一体何でしょうか?
1.クジが引けて当たりが出たらもう1本
2.シール
3.料金が一部返ってくる
+ 答えを見る(こちらをクリック)
3.料金が一部返ってくる
現在ではペットボトルや缶が主流で瓶の物を見かける機会が減りましたが、当時は瓶が主流でした。
そのため、瓶を返却することで瓶の分の料金に相当する10円が返ってきました。当時のレギュラーサイズ(190ml)が35円でしたので、3分の1近くが返って来ていたことになります。
その後、昭和50年代になると、缶が普及していきました。
第3問
1950年代後半には「白黒テレビ」、「洗濯機」、「冷蔵庫」の3つの家電が「三種の神器」と呼ばれていました。
1960年代半には新たに「3C」と呼ばれるものが現れました。「カラーテレビ」、「クーラー」ともう1つは何でしょうか?
1.自動車
2.食器洗い乾燥機
3.掃除機
+ 答えを見る(こちらをクリック)
1.自動車
英語表記の頭文字が「C」で共通していることから、「3C」と呼ばれるようになりました。
中でも特に普及が早かったのがカラーテレビと言われており、1964年(昭和39年)の東京オリンピックがきっかけに売り上げが大きく伸びました。逆に一番普及が遅かったのはクーラーと言われています。
ちなみに、令和時代にはパナソニックが発表する「令和の家電 三種の神器」というものがあり、「4K/8Kテレビ」「冷蔵庫」「ロボット掃除機」が挙げられています。
第4問
昭和の家庭の電話と言えば黒電話。
近年の固定電話には無い強みを持っていますが、それは一体何でしょうか?
1.電話線が必要ない
2.電源が必要ない
3.専用の塗料で自由に色を塗り替えやすい
+ 答えを見る(こちらをクリック)
2.電源が必要ない
現代の一般的な固定電話は電源(コンセント)が必要であるため、停電時には使用できなくなります。
黒電話は電気が必要なことに変わりはありませんが、コンセントから供給されるものではなく電話線を通っている電気を利用しているため、電話線と繋がっていて電話線に電気が通っている限り停電しても使用できます。
そのため、2011年の東日本大震災以降は黒電話と同じように、停電中でも通話ができる電話線のみで動く仕様の固定電話が見直されています。
第5問
1970(昭和45)年1月30日、公衆電話の市内通話料金が3分10円になりました。
それ以前はどのような料金形態だったでしょうか?
1.1時間10円
2.5分10円
3.無制限
+ 答えを見る(こちらをクリック)
3.無制限
当時、長時間公衆電話を占拠する人も少なくなかったため、苦情も大量に入っていたようです。
そこで極端な長時間通話をする人を除けば、だいたいの人が3分程度で通話を終えていたことから、このような時間制限が設けられました。
この新しい形態は「3分打ち切り制」と呼ばれています。
第6問
昭和の時代は連絡手段として普及していたポケベル。
数字の語呂合わせでメッセージを送っていましたが、「至急電話が欲しい」という旨のメッセージは次のうちどれでしょうか?
1.49106
2.500731
3.1052167
+ 答えを見る(こちらをクリック)
1.49106
49106は「至急TEL」の語呂合わせとして使われていました。
「500731」は「ごめんなさい」。「1052167」は「どこにいるの?」です。他にも「0833」で「おやすみ」、「8181」で「バイバイ」などがありました。
そんなポケベルも2019年9月30日にはサービスを完全に終了しています。
第7問
1980年(昭和55年)には東洋陶器(現在のTOTO)より、近年では身近になっているとあるトイレ製品が発売されました。
それは一体何でしょうか?
1.トイレ用芳香剤
2.水に流せるトイレットペーパー
3.ウォシュレット
+ 答えを見る(こちらをクリック)
3.ウォシュレット
ウォシュレットは、TOTOが販売する温水洗浄便座の商品名です。
1964年頃はアメリカから温水洗浄便座を輸入し、主に病院向けに販売していました。そして国内で生産されたウォシュレット発売時にはCMの「おしりだって洗ってほしい」というキャッチコピーが話題にもなりました。
食事時に「おしり」という単語を使ったCMが流れたことでクレームもあったようですが、それ以上のヒットを獲得した商品です。
第8問
1967年(昭和42年)、日本で初めて動く歩道が誕生しました。それはどこでしょうか?
1.名古屋
2.大阪
3.東京
+ 答えを見る(こちらをクリック)
2.大阪
日本初の動く歩道は、大阪の阪急梅田駅に設置されました。
設置から3年後に大阪万博が開催されたことで全国的に有名になりました。
第9問
昭和30年代の後半から40年代の前半には、ある屋内スポーツがブームとなりました。それは何でしょうか?
1.ボウリング
2.アイスホッケー
3.バレーボール
+ 答えを見る(こちらをクリック)
1.ボウリング
人気があったプロ選手たちの影響もあり、ボウリングは大きなブームになりました。
プロの試合も頻繁にテレビで放送され、全国には3000ヶ所以上のボウリング場ができ、休日には数時間待ちも当たり前だったとか。
そんなボウリングもブームのピークが過ぎ、徐々にボウリング場の数も減少していきました。
第10問
1980年代前半、野外で独特の派手な衣装でディスコサウンドに合わせて「ステップダンス」を踊る人が多くみられました。その人たちを何と呼んだでしょうか?
1.竹の子族
2.きのこ族
3.カミナリ族
+ 答えを見る(こちらをクリック)
1.竹の子族
名前の由来には諸説ありますが、衣装を「ブティック竹の子」で購入していたことが「竹の子族」の由来の一つと言われています。
主に首都圏の中学・高校生が参加しており、歩行者天国が開催されていた休日に原宿歩行者天国(ホコ天)に集合し、ホコ天終了時まで踊っていました。
現在も都市部で見られる路上パフォーマンスの先駆け的な存在と言えます。
ちなみにカミナリ族は昭和30年代から40年代頃に用いられた総称で、現在で言う暴走族を指す言葉です。
【高齢者向け】昭和に関する三択クイズ問題【中編10問】


博士
前編10問はどうじゃったかのう?まだ物足りないという人は、次の10問にも挑戦してみるのじゃ!
第11問
「像が踏んでも壊れない」のキャッチフレーズで販売されていた物は次のうちどれでしょうか?
1.眼鏡
2.下駄
3.筆箱
+ 答えを見る(こちらをクリック)
3.筆箱
サンスター文具が発売する「アーム筆入」という商品のCMのキャッチフレーズが、「像が踏んでも壊れない」というものでした。現在も販売されており、像のマークが目印です。近年でも目にしたことのある方も多いのではないでしょうか?
ちなみに、「ポリカーボネイト」という透明度が高く耐衝撃性が強い素材が使われており、この素材は信号機にも使われています。
第12問
1973年(昭和48年)にブームになったボードゲームは何でしょうか?
1.人生ゲーム
2.チェス
3.オセロ
+ 答えを見る(こちらをクリック)
3.オセロ
オセロは意外にも日本生まれのゲームです。
第二次世界大戦が終わって間もない頃、当時少年だった開発者が、碁石を使って生み出した遊びがオセロの原型とされています。白黒の石を使ったゲームという点が囲碁と共通しているのにはこのような背景がありました。
また、試作品が牛乳瓶のフタで作られたこともあり石のサイズは当時と変わらず、牛乳瓶の蓋とほぼ同じ大きさです。
第13問
1964年(昭和39年)にシャープ(当時は早川電機)により発売された日本初の電卓。
価格は53万5000円と非常に高価でした。そして現代の電卓では考えられない重さをしていましたが、何kgあったでしょうか?
1.1kg
2.10kg
3.25kg
+ 答えを見る(こちらをクリック)
3.25kg
これだけの重さがあるので当然サイズも大きく、現代のスーパーのレジのような大きさでした。
車が買える程の値段ということもあり企業向けに作られていた電卓ですが、1970年(昭和45年)頃になると競争が激化し、低価格化が進んだことで誰でも手にできるものに変わっていきました。
そして進歩を重ねて現代のように安価で小型の物になっていきました。
第14問
1983年(昭和58年)に発売された家庭用ゲーム機、ファミリーコンピューター。
任天堂と言えばゲームで世界的に有名ですが、それ以前は主に別の商品を販売していました。
それは一体何でしょうか?
1.子ども服
2.駄菓子や食玩
3.花札・トランプ
+ 答えを見る(こちらをクリック)
3.花札・トランプ
任天堂は1889年に花札の製造から始まり、1902年には日本で初めてトランプの国内生産を始めた企業でもあります。
ちなみに、現在も花札やトランプは製造されています。意識していなかっただけで任天堂の花札やトランプを持っていた方も見えるかもしれません。
第15問
1950年代半ば頃より、学校給食で牛乳が出るようになりました。
それ以前に出されていた飲み物と言えば何だったでしょうか?
1.豆乳
2.脱脂粉乳
3.麦茶
+ 答えを見る(こちらをクリック)
2.脱脂粉乳
地域差はありますが、遅いところでも1970年代前半頃には脱脂粉乳が学校給食から姿を消したようです。
脱脂粉乳は牛乳の中の乳脂肪分を除去したあと、乾燥させて水分も取り除き粉末状にしたものです。これをお湯に溶かしたものを学校給食で飲んでいた世代の方からは「不味い」との声もよく聞かれます。
ちなみに現在では、脱脂粉乳は「スキムミルク」と言う名前で売られています。長期保存が可能で栄養価も高い食品であり、お菓子づくりに使われることもあります。
第16問
1950年代から輸入が始まり、1960年代には国産化が進んだことで国内に広まっていったインスタント製品は何でしょうか?
1.コーヒー
2.ココア
3.チャイ
+ 答えを見る(こちらをクリック)
1.コーヒー
1960年に森永製菓が日本で初めてインスタントコーヒーを発売しました。
これをきっかけに日本でもインスタントコーヒーが広まっていきました。それ以前は問題文のとおり輸入品に頼っていました。
ちなみに、日本初のココアは大正8年(1919年)に森永製菓が発売したミルクココアであり、インスタントコーヒーよりも早く開発されています。
チャイは香辛料が加えられたインドのミルクティーです。
第17問
1965年(昭和40年)に日本で初めて発売され、ブームとなった女性のファッションは何でしょうか?
1.ジーンズ
2.ミニスカート
3.浴衣
+ 答えを見る(こちらをクリック)
2.ミニスカート
帝人が日本で初めてのミニスカート「テイジンエル」を発売したことでブームとなりました。
若い世代だけに留まらず世代を超えた人気がありました。
この当時多くの女性のミニスカートはひざ丈よりやや短い程度であり、さらに短い物はバブル期に登場しています。
第18問
1985年(昭和60年)には、日本初の携帯電話が登場しました。当時の名称は一体何だったでしょうか?
1.携帯式業務用電話
2.ショルダーホン
3.バッグホン
+ 答えを見る(こちらをクリック)
2.ショルダーホン
当時の携帯電話は販売ではなく、NTTが貸し出すといった形でした。
現代の携帯電話と比べて大きいだけではなく電話機の重量も約3kgと重かったため、携帯する際にはショルダーバッグのように肩にかけて持ち出す必要がありました。
位置づけも社外でも使用できる自動車電話(自動車に搭載されていた電話機)となっていました。
第19問
「花金」とは何を指しているでしょうか?
1.花の名前
2.金曜日
3.お酒の名前
+ 答えを見る(こちらをクリック)
2.金曜日
「花金」は1990年代のバブル期に広まった言葉で、「花の金曜日」の略です。
週休二日制の導入により土曜休みの企業が増えたことで、金曜日の晩に飲み歩いて楽しむことを指していました。
バブル崩壊と共にサラリーマンたちにそこまでの余裕が無くなっていったことで徐々に使われなくなっていきました。
第20問
この中で、昭和の時代にオープンしたテーマパークはどれでしょうか?
1.東京ディズニーランド
2.ユニバーサルスタジオジャパン
3.レゴランドジャパン
+ 答えを見る(こちらをクリック)
1.東京ディズニーランド
東京ディズニーランドは1983年(昭和58年)にオープンしました。
それ以来アトラクションやショーのリニューアルを繰り返し行い、長年来園者を楽しませてくれる存在として高い人気を誇っています。
ちなみに、ユニバーサルスタジオジャパンは2001年(平成13年)、レゴランドジャパンは2017年(平成29年)にオープンしました。
特にユニバーサルスタジオジャパンは東京ディズニーランドと並んで人気の高いテーマパークなので、オープンした年に18年の差があるのは意外です。
【高齢者向け】昭和に関する三択クイズ問題【後編10問】


博士
中編10問はどうじゃったかのう?「まだまだ物足りない!」という人は、次の10問にも挑戦してみるのじゃ!
第21問
「ウルトラC」とはなんでしょうか?
1.体操競技の難しい技
2.栄養ドリンク
3.特撮番組
+ 答えを見る(こちらをクリック)
1.体操競技の難しい技
「ウルトラC」とは、「体操競技で最高の得点基準であるCの技術よりさらに難しい、ひねりや旋回などを取り入れた技」のことです。
1964年(昭和39年)の東京オリンピックをきっかけに広く知られるようになった言葉です。
第22問
「陸(おか)サーファー」とはどんな人だったでしょうか?
1.キックボードをする人
2.スケボーをする人
3.サーファーっぽい格好だけした人
+ 答えを見る(こちらをクリック)
3.サーファーっぽい格好だけした人
「陸(おか)サーファー」とは、サーフィンをしないのにサーファーのファッションをマネしただけの人たちです。
1980年頃にサーフィンがブームになり、若者たちの間では「サーフィン=かっこいい」というイメージが広まって行いきました。
そのため、サーフィンはしないけど女性にモテたい男性たちが「陸サーファー」になっていたというわけです。
第23問
現代の会社員の給料は銀行振り込みが当たり前ですが、昭和の時代は違いました。
どのようにして給料を渡していたでしょうか?
1.手渡し
2.郵便で送る
3.宅配便で送る
+ 答えを見る(こちらをクリック)
1.手渡し
昭和の時代、給料は手渡しが当たり前のころがありました。
しかし、1968年(昭和43年)に有名な「三億円事件」が起きたのをきっかけに、給与振り込み制度へと切り替わっていきました。
第24問
「赤信号、みんなで渡れば怖くない」という言葉は漫才から生まれたと言われています。
漫才でこのセリフを用いたコンビはどれでしょうか?
1.ツービート
2.おぼん・こぼん
3.宮川大助・花子
+ 答えを見る(こちらをクリック)
1.ツービート
1980年頃、ツービートの漫才の中に出てくる「赤信号、みんなで渡れば怖くない」というセリフが流行しました。
実際にやるとかなり危ない行為ではありますが、人間の集団心理をよく表した言葉とも言えますね。
第25問
昭和30年代以降に使われていた言葉である「交通戦争」とは、どんな意味でしょうか?
1.交通事故の死者数が急増した様子
2.各地で競い合うように公共交通機関が発達した様子
3.都市部と田舎で道路の整備状況に格差が生まれた様子
+ 答えを見る(こちらをクリック)
1.交通事故の死者数が急増した様子
昭和30年代以降に自動車交通が急成長すると共に、交通事故の発生が急増しました。
交通事故の死者数の水準が、日清戦争での日本の戦死者(2年間で1万7282人)を上回る勢いで増加したことから、この状況は一種の「戦争状態」であるとして、「交通戦争」という言葉が使われるようになりました。
第26問
1965年(昭和40年)に東京である生き物が大量発生し、その駆除のために自衛隊まで出動する事態となりました。
その生き物とはなんでしょうか?
1.ゴキブリ
2.カラス
3.ハエ
+ 答えを見る(こちらをクリック)
3.ハエ
1957年(昭和32年)にゴミの埋め立て地としての利用が開始された「夢の島」をご存じでしょうか。
1965年(昭和40年)、その「夢の島」でハエが大量発生し江東区南西部を中心に大きな被害が発生しました。
その大量発生は東京都だけでは対処できないほどの規模であったため、警視庁・消防・自衛隊が出動し断崖を焼き払う「夢の島焦土作戦」が実行されました。
そんな「夢の島」も1967年(昭和42年)にはゴミの埋め立てが終了し、現在では公園やスポーツ施設が建設された観光地にもなっています。
第27問
「押し屋(おしや)」とは、どんな場所で仕事をする人だったでしょうか?
1.駅のホーム
2.百貨店
3.漁港
+ 答えを見る(こちらをクリック)
1.駅のホーム
「押し屋(おしや)」とは、主に鉄道の朝夕のラッシュ時に列車の扉に挟まりかかった乗客や荷物を車内に押し込む役割の人を指す言葉でした。
主に学生がアルバイトで押し屋をすることが多かったようです。
第28問
昭和の時代、会社員がタバコを吸う場所はどこだったでしょうか?
1.消火器の前
2.喫煙所
3.自分のデスク
+ 答えを見る(こちらをクリック)
3.自分のデスク
昭和の時代は喫煙に関する規制がかなり緩くほとんどの場所でタバコが吸えたため、現在では考えられないような場所でもタバコを吸うことができました。
現代の会社員は喫煙所でタバコを吸うのがルールとなっていますが、昭和の時代は自分のデスクでタバコを吸うのは当たり前でした。
ほかにも、病院の待合室や飛行機の中、職員室などでもタバコを吸うことができました。
第29問
昭和の時代、多くの家庭に置かれていた「魔法瓶」。
魔法瓶の柄として定番だったものはなんでしょうか?
1.星
2.水玉
3.花
+ 答えを見る(こちらをクリック)
3.花
昭和の時代に広く普及していた魔法瓶は、花柄が定番となっていました。
1967年(昭和42年)に、大阪の魔法びんメーカー「エベレスト魔法びん」が花柄の魔法瓶を発売したことがきっかけとなり、他のメーカーもそれを追うように花柄の魔法瓶の製造を始めたことで花柄の魔法瓶が全国的に広まっていきました。
第30問
引退時のスピーチで「わが巨人軍は永久に不滅です」と語った元プロ野球選手と言えば誰でしょうか?
1.駒田徳広
2.長嶋茂雄
3.桑田真澄
+ 答えを見る(こちらをクリック)
2.長嶋茂雄
1974年(昭和49年)、長嶋茂雄さんが引退を発表しました。
引退時のスピーチで「わが巨人軍は永久に不滅です」と語ったことはとても有名です。
ちなみに…スピーチの原稿には「永久」ではなく「永遠」と書かれていたそうです。

博士
今回のクイズ問題は以上じゃ!君は何問解けたかな?
このサイトではいろんな脳トレクイズを紹介しているから、ぜひ他のクイズにも挑戦してみるのじゃ!