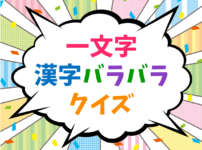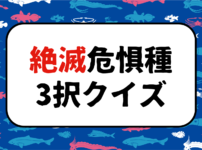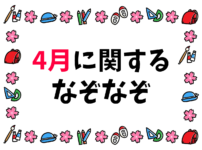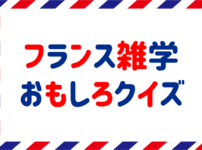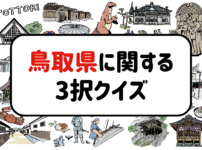博士
今回は夏の食べ物に関するクイズを出題するぞ!全問正解目指して頑張るのじゃ。
【夏の食べ物に関するクイズ】高齢者向け!簡単・面白い雑学問題【前編10問】


博士
まずは10問出題するぞぉ!3つの選択肢の中から正しいものを一つ選ぶのじゃ
第1問
昔、日本で栽培されていたスイカには縞模様がありませんでした。
どんなスイカだったでしょうか?
1.黒色で無地
2.白色で無地
3.緑色で無地
+ 答えを見る(こちらをクリック)
1.黒色で無地
スイカと言えば緑色に黒の縞模様を思い浮かべますが、昔は黒色で無地の「鉄かぶと」と呼ばれるスイカが一般的でした。
現在一般的に知られている緑色に黒の縞模様のスイカが広まったのは、昭和初期からと言われています。
ちなみに、黒色で無地のスイカ自体は現代にも存在しています。
第2問
「夕顔(ユウガオ)」という野菜はある食品に加工することができます。
その食品とはなんでしょうか?
1.メンマ
2.春雨
3.かんぴょう
+ 答えを見る(こちらをクリック)
3.かんぴょう
夕顔は、かんぴょうの材料となっている野菜です。
名前はアサガオに似ていますが、夕顔はウリ科、アサガオはヒルガオ科というものに分類されるため直接関係があるわけではありません。
ウリ科の野菜であるため煮物などにして食べることもできます。
第3問
千葉県富津市で「はかりめ」と呼ばれている夏が旬の魚はなんでしょうか?
1.アジ
2.アナゴ
3.ウナギ
+ 答えを見る(こちらをクリック)
2.アナゴ
千葉県富津市ではアナゴのことを「はかりめ」と呼んでいます。
アナゴの姿が魚市場で使われる「棹はかり」という道具に似ていることから、アナゴを「はかりめ」と呼ぶようになったと言われています。
煮アナゴをご飯にのせた「はかりめ丼」という富津市のご当地メニューも有名です。
第4問
ブルーベリーは何に効果があると言われているでしょうか?
1.目の疲労回復
2.花粉症予防
3.歯周病の改善
+ 答えを見る(こちらをクリック)
1.目の疲労回復
ブルーベリーは、目の疲労回復に効果があると言われています。
ブルーベリーに含まれる「アントシアニン」という成分には目の疲労回復や視力低下・眼病予防の効果が期待できます。
「ブルーベリーを採ると目が良くなる」とよく言われています。しかし実際には、既に低下した視力が回復するほどの効果は得られません。
第5問
キュウリが熟すと何色になるでしょうか?
1.赤色
2.白色
3.黄色
+ 答えを見る(こちらをクリック)
3.黄色
キュウリは熟すと黄色に変化します。私たちが日頃食べているキュウリは未成熟な実です。
江戸時代頃、キュウリは熟して黄色になったものを食べていました。
しかし、熟したキュウリはみずみずしさや歯ごたえが失われているため、あまり美味しくありません。
第6問
ドジョウは小さい魚でありながら、1匹で別のある魚1匹に匹敵する栄養があると言われています。
その魚とはなんでしょうか?
1.ナマズ
2.ウナギ
3.アナゴ
+ 答えを見る(こちらをクリック)
2.ウナギ
昔から「ウナギ一匹、ドジョウ一匹」と言う言葉があり、ドジョウ1匹でウナギ1匹に匹敵する栄養があると言われていました。
ドジョウはウナギよりも脂が少ない分さっぱりしており、カルシウムはウナギの9倍も含まれています。
また、カルシウムの吸収を促すビタミンDも豊富に含まれています。
第7問
プルーンとはどんな果物でしょうか?
1.バナナ
2.ミカン
3.スモモ
+ 答えを見る(こちらをクリック)
3.スモモ
プルーンとは、西洋スモモのことです。
スモモは「日本スモモ」と、ヨーロッパ原産の「西洋スモモ」の2つに分けることができます。
日本スモモは「プラム」、西洋スモモは「プルーン」と呼ばれています。
プルーンはドライフルーツやシロップに加工されることが多い果物としても知られています。国内で生産されたプルーンは生食用としても流通しています。
第8問
ドラゴンフルーツとはなんの実でしょうか?
1.ヤシ
2.サトウキビ
3.サボテン
+ 答えを見る(こちらをクリック)
3.サボテン
ドラゴンフルーツとは、サボテンの実のことです。
「ピタヤ」とも呼ばれており果肉の色によって「ホワイトピタヤ」「イエローピタヤ」「レッドピタヤ」と呼び分けがされています。
また、果肉の表面にはゴマ粒のように黒くて小さい種が多く見られますが、そのまま食べることができます。
第9問
ニンニクを食べた後に摂取すると臭いを緩和できると言われているものはなんでしょうか?
1.牛乳
2.エナジードリンク
3.ビール
+ 答えを見る(こちらをクリック)
1.牛乳
ニンニクを食べた後に、牛乳を摂取すると臭いを緩和できると言われています。
ニンニクの臭い成分「アリシン」は、タンパク質や脂質と結合しやすいという特徴があり、それらの成分と結合したアリシンは臭いが抑制されます。
そのため、脂肪分を含む牛乳を飲むとアリシンが発する臭いを抑えることができ、口臭予防が期待できます。
第10問
「そうめん」と「ひやむぎ」の違いはなんでしょうか?
1.原材料
2.太さ
3.長さ
+ 答えを見る(こちらをクリック)
2.太さ
「そうめん」と「ひやむぎ」の違いは、太さです。
そうめんは「直径1.3mm未満」、ひやむぎは「直径1.3mm以上、1.7mm未満」とされています。そして、1.7mm以上の麵になると「うどん」に分類されます。
このような定義が決まっており、機械であれば正確な太さで生産することができます。しかし、手延べ麺の場合はいくら熟練の技であっても僅かな誤差が生じてしまいます。
そのため、手延べ麺の場合に限り1.7mm未満であれば「そうめん」か「ひやむぎ」の好きな方を名乗ることができます。
【夏の食べ物に関するクイズ】高齢者向け!簡単・面白い雑学問題【中編10問】


博士
前編10問はどうじゃったかのう?まだ物足りないという人は、次の10問にも挑戦してみるのじゃ!
第11問
心太(ところてん)の原材料はなんでしょうか?
1.海藻
2.山菜
3.樹液
+ 答えを見る(こちらをクリック)
1.海藻
心太の原材料は、テングサやオゴノリなどの海藻です。
それらを茹でて煮溶かすことで出来た寒天質を冷やし固めたものが心太です。
心太は腸内で消化されないため栄養価が殆どない食品ではありますが、食物繊維を含むため整腸作用が期待できます。
第12問
冷やし中華発祥の国はどこでしょうか?
1.日本
2.中国
3.韓国
+ 答えを見る(こちらをクリック)
1.日本
冷やし中華は日本発祥の料理です。中国の冷やし麺「涼拌麺」が元になったとも言われていますが、製法が違っており日本独自のメニューとなっています。
冷やし中華は海外にも広まっており、中国では「日本式涼拌麺」、韓国では「冷ラーメン」と呼ばれています。
第13問
トウモロコシの髭の正体はなんでしょうか?
1.根
2.めしべ
3.葉
+ 答えを見る(こちらをクリック)
2.めしべ
トウモロコシの髭は、めしべです。
トウモロコシの髭(めしべ)は全て1つ1つの粒と繋がっており、髭の数と粒の数は同じになります。
つまり、髭がたくさん付いているトウモロコシほど実がたくさん詰まっているという証拠です。
また、トウモロコシの粒の数は必ず偶数になります。
第14問
昔、ヨーロッパで「毒リンゴ」と呼ばれていた夏野菜はなんでしょうか?
1.ナス
2.トマト
3.キュウリ
+ 答えを見る(こちらをクリック)
2.トマト
トマトは昔、ヨーロッパで「毒リンゴ」と呼ばれていました。
1500年代、ヨーロッパの貴族たちが使っていた食器類の多くには鉛が使われていました。
その鉛がトマトの酸味によって溶け出したことで、鉛中毒になる貴族が多くいました。
そのせいもあり「トマト=有毒」という誤解を受けて食べられなくなり、その誤解が解けた後も暫くは観賞用として扱われていました。
改めて食用として広まっていったのは18世紀頃と言われています。
第15問
骨が非常に多く、「骨切り」という処理が必要な魚といえばなんでしょうか?
1.ハモ
2.マグロ
3.カツオ
+ 答えを見る(こちらをクリック)
1.ハモ
「骨切り」という処理が必要な魚はハモです。
ハモは約3500本もの骨があり、うち約600本は小骨であると言われています。
そのため、薄い皮を残して身の中の小骨を垂直に刻む「骨切り」という技術が欠かせないものになっています。
第16問
アイスクリームの賞味期限はだいたいどれくらいでしょうか?
1.1年
2.10年
3.賞味期限は無い
+ 答えを見る(こちらをクリック)
3.賞味期限は無い
アイスクリームに賞味期限はありません。
マイナス18度以下でしっかり冷凍保存されていれば微生物は増殖しません。
そのため、品質の劣化が殆ど起こらないアイスクリームには賞味期限を設定しなくても良いということになっています。
第17問
スイカに似た香りがすることから「香魚」とも呼ばれる魚といえばなんでしょうか?
1.アユ
2.ヤマメ
3.イワナ
+ 答えを見る(こちらをクリック)
1.アユ
水質が良い河川で獲れる若アユはスイカにも似た良い香りがすることから、「香魚」とも呼ばれています。
川魚と言えば泥臭いイメージがありますが、アユは岩や小石に生えるコケを食べていることから良い香りがするようになったと言われています。
第18問
国産パイナップルは夏に旬を迎えます。
パイナップルと言えば酢豚に入っていることがありますが、その理由はなんでしょうか?
1.酸味を出すため
2.肉を柔らかくするため
3.香りをつけるため
+ 答えを見る(こちらをクリック)
2.肉を柔らかくするため
パイナップルが酢豚に入っているのは、肉を柔らかくするためです。
パイナップルには「プロメライン」というタンパク質分解酵素が含まれており、一緒に調理することで肉が柔らかくなります。
また、消化吸収が良くなることから胃もたれの予防も期待できます。
第19問
ナスは薬用としても活用することができる野菜です。
ナスのヘタは何に効果がある薬になるでしょうか?
1.口内炎
2.糖尿病
3.骨粗しょう症
+ 答えを見る(こちらをクリック)
1.口内炎
ナスのヘタは、口内炎や歯槽膿漏に効果がある薬になります。
ナスのへたの黒焼き粉末状にして食塩を混ぜたものは歯磨き粉として使うことができ、江戸時代にもナスのヘタの黒焼きが歯磨きに利用されていたと言われています。
第20問
かき氷はいつ頃から食べられているでしょうか?
1.平安時代
2.江戸時代
3.昭和時代
+ 答えを見る(こちらをクリック)
1.平安時代
かき氷は平安時代には既に食べられていたと言われています。
清少納言が書いた「枕草子」にはかき氷と思われるものを食べた旨の文章が記されています。
当時は夏に氷を確保することが困難であったため、貴族しか食べることができない贅沢品でもありました。
【夏の食べ物に関するクイズ】高齢者向け!簡単・面白い雑学問題【後編10問】


博士
中編10問はどうじゃったかのう?「まだまだ物足りない!」という人は、次の10問にも挑戦してみるのじゃ!
第21問
有名なそうめん「揖保乃糸」が生産されている都道府県はどこでしょうか?
1.青森県
2.兵庫県
3.三重県
+ 答えを見る(こちらをクリック)
2.兵庫県
誰もが知っている有名なそうめん「揖保乃糸」は兵庫県手延素麺組合が有する商標です。
現在では全国生産量の35%を占めており、日本一となっています。
第22問
次のうち、種に毒がある夏野菜はどれでしょうか?
1.モロヘイヤ
2.ピーマン
3.トウガラシ
+ 答えを見る(こちらをクリック)
1.モロヘイヤ
モロヘイヤの種には、毒が含まれています。
もしも種や実を少量でも摂取した場合、めまいや嘔吐などの中毒を起こすため絶対に食べてはいけません。
実のついたモロヘイヤを食べた牛が死亡するという事例も報告されています。
家庭菜園でモロヘイヤを育てる場合は注意しましょう。
第23問
柚子は夏と冬に旬を迎えます。
夏に収穫される柚子はなんと呼ばれているでしょうか?
1.黄玉
2.赤玉
3.青玉
+ 答えを見る(こちらをクリック)
3.青玉
7月~8月には、まだ熟していない状態の柚子が収穫されます。
その柚子は「青玉」と呼ばれており、主に柚子胡椒などの薬味として利用されています。
第24問
高級食材のアワビはいつ頃から食べられているでしょうか?
1.縄文時代
2.鎌倉時代
3.江戸時代
+ 答えを見る(こちらをクリック)
1.縄文時代
アワビは、縄文時代にはすでに食べられていたことが分かっています。
さらに、縄文人はアワビの殻を食器としても活用していました。
第25問
近年話題になっている韓国の夏の食べ物「ピンス」とは、日本で言えばどんな食べ物でしょうか?
1.水羊羹
2.かき氷
3.ざるそば
+ 答えを見る(こちらをクリック)
2.かき氷
「ピンス」とは、韓国のかき氷のことです。
氷の上にあずきやフルーツ、アイスクリームなどが盛られておりボリュームがあります。
近年では夏の人気デザートの1つになっています。
第26問
縁日の定番メニューの1つであるりんご飴は、世界各地で食べられています。
では、フランス語で「りんご飴」を意味する「Pomme d'amour」を直訳するとどうなるでしょうか?
1.甘いりんご
2.愛のりんご
3.飴のりんご
+ 答えを見る(こちらをクリック)
2.愛のりんご
りんご飴は、シロップや飴などで生のリンゴ果実をコーティングしたお菓子です。
日本では縁日の定番ですが、海外ではハロウィンの定番のお菓子の1つにもなっています。
同じお菓子でも国によって呼び方が違っており、フランス語でりんご飴を意味する「Pomme d'amour」を直訳すると、「愛のりんご」という意味になります。
第27問
アイスクリームのコーンは、とある世界的なイベントが誕生のきっかけだと言われています。
そのイベントとはなんでしょうか?
1.オリンピック
2.サッカーワールドカップ
3.万博
+ 答えを見る(こちらをクリック)
3.万博
アイスクリームのコーンが誕生したきっかけは、1904年にアメリカで開催された「セントルイス万博」です。
アイスクリームは当時から人気があり、暑かったことから飛ぶように売れたそうです。
しかし、その結果アイスクリームよりも先に容器がなくなってしまいました。そんなアイスクリーム屋に声をかけたのが、隣のワッフル屋でした。
暑かったこともあり売れ行きがイマイチだったワッフルを円錐の形に巻き上げ、それにアイスを乗せることを提案しました。
それが評判となり、現在のコーンへと形を変えていきました。
第28問
夏に旬を迎える「ビタミンCの王様」と呼ばれる果物があります。
その正体はなんでしょうか?
1.アセロラ
2.スイカ
3.パイナップル
+ 答えを見る(こちらをクリック)
1.アセロラ
アセロラは、西インド諸島や熱帯アメリカが原産とされる果物です。
ビタミンCを豊富に含んでいることから「ビタミンCの王様」とも呼ばれています。
熟したアセロラは痛みやすく、2~3日しか鮮度を保てないため生の物はほとんど出回っていません。
ジュースやジャムなどに加工されて流通しています。
第29問
冷奴の薬味と言えばショウガが定番ですが、石川県では他の薬味が人気です。
それはなんでしょうか?
1.柚子胡椒
2.カラシ
3.ワサビ
+ 答えを見る(こちらをクリック)
2.カラシ
石川県では、冷奴にカラシをつけて食べる人が多くいます。
能登地方には豆腐の中にカラシが入った「茶碗豆腐」という食べ物があることから、冷奴の薬味としてもカラシが定番になったと考えられています。
第30問
冷製パスタは1970年代のイタリアで誕生したと言われています。
では、その世界初の冷製パスタに使われていたメインの具はなんでしょうか?
1.ベーコン
2.マッシュルーム
3.キャビア
+ 答えを見る(こちらをクリック)
3.キャビア
1970年代にイタリアのグアルティエーロ・マルケージというシェフが、冷たいキャビアのパスタを作ったのが冷製パスタの起源であるという説があります。

博士
今回のクイズ問題は以上じゃ!君は何問解けたかな?
このサイトではいろんな脳トレクイズを紹介しているから、ぜひ他のクイズにも挑戦してみるのじゃ!