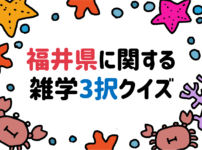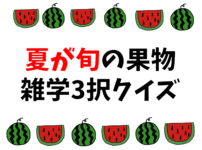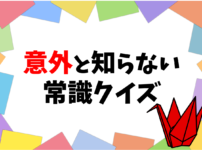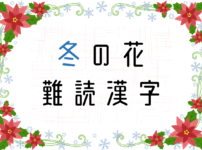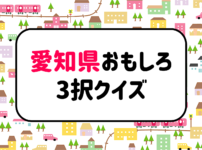博士
今回は1月に関する雑学クイズを出題するぞぉ!全問正解目指して頑張るのじゃ!
【高齢者向け】1月に解きたい雑学クイズ問題【前編10問】


博士
まずは10問出題するぞぉ!3つの選択肢の中から正解だと思うものを一つ選ぶのじゃ!
第1問
お正月の遊びの中で、江戸時代に禁止令が出されたものがありました。
それはなんでしょうか?
1.福笑い
2.コマ
3.凧揚げ
+ 答えを見る(こちらをクリック)
3.凧揚げ
江戸時代、凧揚げは『いかのぼり』と呼ばれていました。
しかし、いかのぼり同士がぶつかり落下する事故が多発したり、喧嘩に発展するなどのトラブルも起こりました。
そこで幕府は『いかのぼり禁止令』を出しましたが、庶民の中にこれは「いかのぼりではなく、たこのぼりだ」と屁理屈をこね、禁止令を無視する者が現れました。
幕府も禁止令を出したとは言え多少のことには目をつむっていたため、イカからタコに名前を変え庶民に親しまれる遊びとして残り、現在の凧揚げへと名前を変えていきました。
第2問
初夢に見ると縁起が良いと言われるものに【一富士二鷹三茄子】があります。
実はこれには続きがあり、六番まで存在します。
では、五番目はなんでしょうか?
1.煙草(タバコ)
2.酒
3.賭博
+ 答えを見る(こちらをクリック)
1.煙草
一富士二鷹三茄子の後には、四扇(しおうぎ)、五煙草(ごたばこ)、六座頭(ろくざとう)と続きます。
六の座頭は剃髪した琵琶法師の座に所属する者を指します。
第3問
お正月にはやってはいけないと言われていることがあります。
それは一体なんでしょうか?
1.入浴
2.掃除
3.早起き
+ 答えを見る(こちらをクリック)
2.掃除
お正月には掃除をしてはいけないと言われています。
掃除の中でも特に玄関先の掃き掃除は、せっかく来てくれた年神さまを追い出してしまうことになると言われています。
年末の大掃除も年神様を気持ちよく迎えるためのものですので、年明けに持ち込まないように計画的に終わらせておきたいものですね。
第4問
鏡餅の上に乗っている果物は見た目こそ似ていますが、実はミカンではありません。
では、鏡餅の上に乗っている果物はなんでしょうか?
1.だいだい
2.かぼす
3.いよかん
+ 答えを見る(こちらをクリック)
1.だいだい
鏡餅の上に乗っているのはミカンだと思う方も多いかと思いますが、実は『橙(だいだい)』というミカンの仲間の果物です。
ミカンは春になると実が熟しきって木から落ちてしまいます。しかし、橙の場合は春になっても実が落ちません。
さらに前になった実がついたまま、新しい実がなり一度なった実は4~5年程は木から落ちません。
そのことから、『子孫が代々反映しますように』との願いが込められています。
第5問
アボガドは栄養価が高いことから『森の〇〇〇』と呼ばれています。
空欄に当てはまるものはなんでしょうか?
1.診療所
2.バター
3.キノコ
+ 答えを見る(こちらをクリック)
2.バター
お寿司やハンバーガーなどに使われることもある「アボカド」。
国内に出回っているものは輸入品がほとんどですが、国産品も存在し1月はそれが出回る時期でもあります。
アボカドの果肉の20%は脂肪分です。脂肪とは言っても、『不和脂肪酸』というもので、血液をサラサラにしたり、コレステロール減少に効果があると言われているものです。
他にも豊富な栄養を持っていることから『森のバター』と呼ばれています。
しかし、加熱すると成分が壊れるためできる限り生で食べるのが良いとされています。
第6問
ナマコは冬に旬を迎えます。
ユニークな姿をしているナマコですが、身を守るために変わった行動をとります。
それは一体なんでしょうか?
1.おならをする
2.内臓を吐き出す
3.石のように固くなる
+ 答えを見る(こちらをクリック)
2.内臓を吐き出す
ナマコは内臓を吐き出すことで敵がそれに気を取られていたり、食べている間に逃げます。
その内臓も時間が経てば再生し、元通りになります。まるでトカゲの尻尾のようですね。
第7問
伝統的であり、童謡の『お正月』の歌詞にも登場する「コマ」。
実はコマは日本だけの文化ではなく、外国にも様々なコマが存在しており、かなり昔から人類に親しまれています。
では、世界最古のコマはどこの国で誕生したとされているでしょうか?
1.日本
2.中国
3.エジプト
+ 答えを見る(こちらをクリック)
3.エジプト
現存するもので、世界最古のコマと言われるものはエジプトで発掘されました。
紀元前1400年~2000年前のものと言われています。
日本でも平城京跡などからもコマと思われる出土品が見つかっています。
第8問
童謡『お正月』の作曲者は誰でしょうか?
1.滝廉太郎
2.小林幸子
3.福沢諭吉
+ 答えを見る(こちらをクリック)
1.滝廉太郎
滝廉太郎は他にも『荒城の月』や『箱根八里』などでも知られています。
ちなみに、『お正月』は、2007年(平成19年)には「日本の歌百選」に選ばれています。
第9問
1949年(昭和24年)より、お年玉付き年賀はがきの販売が開始されました。
第1回の特等の景品はなんだったでしょうか?
1.ミシン
2.ラジオ
3.掃除機
+ 答えを見る(こちらをクリック)
1.ミシン
初代の賞品は特等から6等まであり、その内容(賞品)は下記の通りです。
- 特等…ミシン
- 1等…純毛服地
- 2等…学童用グローブ
- 3等…学童用こうもり傘
- 4等…はがき入れ
- 5等…便せん
- 6等…切手シート
第10問
お節料理には様々な意味が込められています。
そのうちの1つ『栗金団』に込められた意味はなんでしょうか?
1.魔除け
2.金運
3.無病息災
+ 答えを見る(こちらをクリック)
2.金運
栗金団は、黄金に例えて金運を呼ぶ縁起物とされています。
ちなみに、岐阜県には『栗きんとん』という和菓子がありますが、おせちの物とは全くの別物です。
【高齢者向け】1月に解きたい雑学クイズ問題【中編10問】


博士
前編10問はどうじゃったかのう?まだ物足りないという人は、次の10問にも挑戦してみるのじゃ!
第11問
初詣で甘酒を振る舞う神社がありますが、その理由はなんでしょうか?
1.お屠蘇(おとそ)の代わり
2.甘酒には魔除けの効果があるとされているから
3.甘いものを飲むと金運を呼ぶとされているから
+ 答えを見る(こちらをクリック)
1.お屠蘇(おとそ)の代わり
お屠蘇(おとそ)とは、お正月に飲まれる縁起物のお酒があります。
漢方薬をお酒に浸した薬酒であり無病息災を願い、一年の邪気を払って長寿を願うとも言われています。
当然、お酒なので子どもやお酒が苦手な人は飲めません。
そこで、老若男女問わず美味しく飲める甘酒を振る舞うようになったと言われています。
第12問
1月7日には七草粥を食べる風習があります。
春の七草の1つに『ぺんぺん草』とも呼ばれるものがありますが、それは一体なんでしょうか?
1.たんぽぽ
2.ナズナ
3.オジギソウ
+ 答えを見る(こちらをクリック)
2.ナズナ
なぜナズナがぺんぺん草と言われるようになったかと言うと、『ぺんぺん』というのは三味線を弾く時の擬音です。
ナズナの実の形が三味線のバチに似ていることから、ぺんぺん草と呼ばれるようになったと言われています。
ナズナには解熱や利尿作用の効能があると言われています。
第13問
1月の第2月曜日は「成人の日」です。
成人式が開始される以前に、ある県で成人式の先駆けと言える行事が行われました。
それは一体どこの県でしょうか?
1.東京都
2.群馬県
3.埼玉県
+ 答えを見る(こちらをクリック)
3.埼玉県
1946年(昭和21年)11月22日、埼玉県蕨市で太平洋戦争終結後に次世代を担う青年たちを励まそうと行われた『青年祭』というものがありました。
これが日本政府の目にとまり、今の成人式へと繋がったと言われています。
第14問
1月の誕生石はなんでしょうか?
1.ダイヤモンド
2.ガーネット
3.パール
+ 答えを見る(こちらをクリック)
2.ガーネット
ガーネットは『真実』『友愛』といった意味を持っています。
赤、オレンジ、黄色、緑、黒、ピンクなど、様々な色合いを持っている宝石です。
中でも特に希少な青色のガーネットは、日光の下では青緑色ですが、蛍光灯など人工的な灯りの下では紫色に変化するという特徴があります。
第15問
お正月に食べるお雑煮に欠かせないのが「お餅」です。
西日本では丸餅が多く、東日本では角餅を使用することが多い傾向にあります。
このように分かれたのには江戸時代が関係していますが、関東に角餅が多い理由はなんでしょうか?
1.角餅の方が量産しやすいから
2.角餅の日持ちが良かったから
3.角餅の角が刀を連想させ、武士に好まれたから
+ 答えを見る(こちらをクリック)
1.角餅の方が量産しやすいから
江戸時代の人口は、江戸やその近辺に集中していました。
丸餅は手で1つ1つ丸めて作るため、手間がかかります。
その一方で、角餅はのし餅を切ることで用意できるため丸餅と比べて量産がしやすく人口が多い江戸で売るのに向いていました。
角餅(のし餅)は、武士が多くいた東日本では、戦の前に『敵をのす』との縁起担ぎになっていたとも言われています。
西日本の丸餅には、『角が立たず円満に過ごせるように』との意味が込められていたと言われています。
第16問
春や秋に行われる「火災予防運動」。
それらの運動では、家庭や公共施設などを対象に広報活動が行われています。
そして毎年1月26日は、ある特定のものの防火を呼び掛ける日とされています。
その特定のものとは一体なんでしょうか?
1.山
2.文化財
3.墓地
+ 答えを見る(こちらをクリック)
2.文化財
1949年(昭和24年)1月26日、現存する世界最古の木造建造物である法隆寺金堂の壁画が焼損しました。
このことから、家事から文化財を守り、国民一般の文化財愛護に関する意識の高揚を図ることを目的とし、1955年(昭和30年)より1月26日は『文化財防火デー』とされました。
どんな時期、どんな場所でも火の取り扱いには注意したいものですね。
第17問
フランスの新年のお祝いに欠かせないお菓子(パイ)に、『ガレット・デ・ロワ』というものがあります。
このお菓子の中にはある意外なものが入っていて、切り分けた時にそれが出てきたらみんなから祝福されます。
その中に入っている意外なものとはなんでしょうか?
1.コイン
2.ボタン
3.陶器製の人形
+ 答えを見る(こちらをクリック)
3.陶器製の人形
ガレット・デ・ロワの中にはフェーブ(そら豆という意味)と呼ばれる陶器製の人形が仕込まれています。
もともとは乾燥した豆を入れていたのが人形に変化していきました。
ちょっとした運試しのようで面白そうですね。
第18問
お正月と言えば、日本では年に1回お祝いする特別な日です。
しかし、お正月にあたるお祝いを年に3回行う国があります。
その国はどこでしょうか?
1.ロシア
2.タイ
3.アメリカ
+ 答えを見る(こちらをクリック)
2.タイ
西暦の正月(1月1日)、中華圏の旧正月(1月下旬~2月中旬)、そして水かけ祭りとしても知られる『ソンクラーン』と言うタイの旧正月(4月)。これら3つの正月が祝われています。
実は旧正月を祝う国自体は珍しくはないのですが、他国の旧正月まで祝うのは珍しいと言えます。
第19問
日本では神社に絵馬を奉納する文化がありますが、元々は今のような絵が描かれた板ではありませんでした。
では、元々は何が奉納されていたでしょうか?
1.生きた馬
2.馬の毛で作った筆
3.馬のよだれ
+ 答えを見る(こちらをクリック)
1.生きた馬
生馬を神に献上していたのが由来と言われます。
奈良時代になると馬をかたどった木馬に変わり、平安時代には板立馬へと変化し、現在のような形の絵馬になったとされています。
近年では、若い世代も興味を示すようなアニメのキャラクターが描かれた絵馬も現れています。
第20問
神社に参拝する際に手を清める場所を『手水舎(ちょうずや)』と言い、清める必要があるのは初詣でも例外ではありません。
ここでは手を清めるのはもちろんですが、手以外にも清めるべき体の部位があります。
それは一体どこでしょうか?
1.口
2.足
3.おしり
+ 答えを見る(こちらをクリック)
1.口
清める際には「左手→右手→口→使った柄杓の柄」の順に清めます。
口を清める(口をすすぐ)際には柄杓に口をつけてはいけませんし、口に含んだ水を飲んでもいけません。
手と口を清めることで、魂も洗い清めるという意味があるとされています。
【高齢者向け】1月に解きたい雑学クイズ問題【後編10問】


博士
中編10問はどうじゃったかのう?「まだまだ物足りない!」という人は、次の10問にも挑戦してみるのじゃ!
第21問
1月は旧暦で何と呼ぶでしょうか?
1.如月
2.睦月
3.霜月
+ 答えを見る(こちらをクリック)
2.睦月
正月に家族や親戚が一同に集まって宴をし、「睦み合う(むつみあう=お互いに親しくすること、仲睦まじい様子)」から「睦び月(むつびつき)」となり、それが「睦月」となったという説があります。
第22問
1月の星座はどれでしょうか?
1.おとめ座
2.ふたご座
3.やぎ座
+ 答えを見る(こちらをクリック)
3.やぎ座
12月22日~1月19日までの間に生まれた人は「やぎ座」、1月20日~2月18日までの間に生まれた人は「みずがめ座」となっています。
第23問
「元旦」の説明として正しいものはどれでしょうか?
1.1月1日の午前中を指している
2.1月1日の午後を指している
3.1月1日終日を指している
+ 答えを見る(こちらをクリック)
1.1月1日の午前中を指している
「元日」は「1月1日終日」を、「元旦」は「1月1日の午前中」を指しています。
第24問
毎年1月に東京ドームで開催される「ライスボウル」という大会は、どのスポーツの大会でしょうか?
1.テニス
2.アメリカンフットボール
3.バレーボール
+ 答えを見る(こちらをクリック)
2.アメリカンフットボール
「ライスボウル」は、アメリカンフットボールの日本一のチームを決定する大会です。
現在の大会正式名称は「アメリカンフットボール日本選手権 プルデンシャル生命杯 第○○回ライスボウル」です。
第25問
現在は18歳からが成人ですが、成人式の対象年齢は18歳の自治体と20歳の自治体どちらが多いでしょうか?
1.18歳
2.20歳
3.ほぼ同じくらい
+ 答えを見る(こちらをクリック)
2.20歳
成人の年齢が18歳になってからも、ほとんどの自治体で対象年齢は20歳のままです。
その理由には、「18歳は進学や就職を控えていて、参加が難しい人が多い」「飲酒や喫煙が認められる20歳で、大人としての自覚を促す」などが挙げられます。
第26問
箱根駅伝の第1回大会は、1920年(大正9年)に開催されました。
その第1回大会の出場校の数はいくつでしょうか?
1.4校
2.8校
3.15校
+ 答えを見る(こちらをクリック)
1.4校
箱根駅伝の第1回大会には、慶應義塾大学・東京高等師範学校(現:筑波大学)・明治大学・早稲田大学の4校が出場しました。
呼びかけられた多くの大学・旧制専門学校・師範学校は選手を10人そろえられず参加を断念していました。
午前中に授業を行って午後にスタートしていたため、ゴールした頃には夜になっていたそうです。
第27問
成人式の日に女性が着ることが多い振袖は、どんな人が着る衣装とされているでしょうか?
1.未婚の女性
2.既婚の女性
3.その年に20歳になる女性
+ 答えを見る(こちらをクリック)
1.未婚の女性
現代の成人式では、多くの女性が振袖を着ています。
その由来は、振袖が明治時代から未婚女性の第一礼装とされてきたことだと言われています。
第28問
伊達巻きは右巻きと左巻き、どちらが縁起が良いでしょうか?
1.右巻き
2.左巻き
3.巻き方で縁起の良さは変わらない
+ 答えを見る(こちらをクリック)
1.右巻き
右巻きが「陽(プラスのエネルギー)」、左巻きが「陰(マイナスのエネルギー)」を表すとされています。
よって、右巻きの方が縁起が良いと言えます。
第29問
1月は牡蠣が旬を迎える時期です。
牡蠣には栄養が豊富であることからついた別名がありますが、それはなんでしょうか?
1.海のバター
2.海のミルク
3.海の肉
+ 答えを見る(こちらをクリック)
2.海のミルク
牡蠣は「身が乳白色であること」と「牛乳のようにバランスよく栄養を含んでいること」から「海のミルク」と呼ばれるようになりました。
第30問
成人の日は1月の第2月曜日ですが、昔は日付が決まっていました。
正しいものはどれでしょうか?
1.1月5日
2.1月15日
3.1月25日
+ 答えを見る(こちらをクリック)
2.1月15日
現在の成人の日は毎年1月の第2月曜日ですが、1999年(平成11年)までは1月15日と決まっていました。

博士
今回のクイズ問題は以上じゃ!君は何問解けたかな?
このサイトではいろんな脳トレクイズを紹介しているから、ぜひ他のクイズにも挑戦してみるのじゃ!