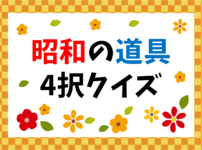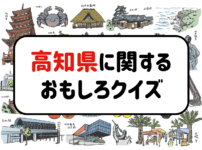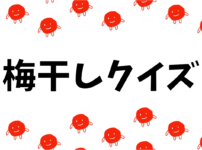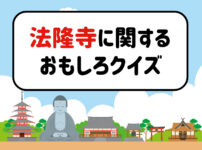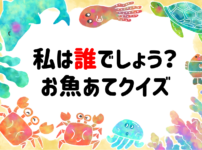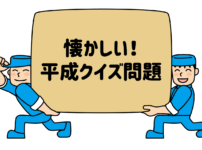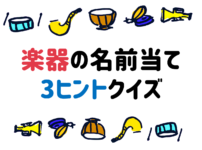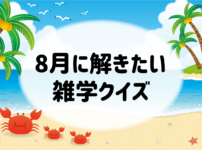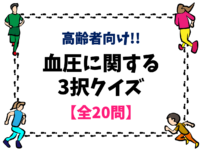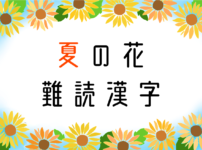博士
今回は9月に関する雑学クイズを出題するぞ!全問正解目指して頑張るのじゃ!
【高齢者向け】9月に関する雑学&豆知識おもしろクイズ問題【前編10問】


博士
まずは10問出題するぞぉ!3つの選択肢を出すから正解だと思うものを一つ選ぶのじゃ!
第1問
9月の第3月曜日は敬老の日です。
では、日本で初めて敬老の日の元になった行事が行われた県はどこでしょうか?
1.愛知県
2.岩手県
3.兵庫県
+ 答えを見る(こちらをクリック)
3.兵庫県
1947年(昭和22年)、兵庫県多可郡野間谷村(現在の多可町)で始まった『としよりの日』が敬老の日の元になった行事と言われています。
これは、「老人を大切にし、お年寄りの知恵を借りて村づくりをしよう」という行事でした。
この行事を全国に広めようという動きの中で『老人の日』と名前を変え、1966年(昭和41年)には祝日として『敬老の日』が成立しました。
第2問
日本では月の模様が『餅をつくウサギ』に見えます。
インドネシアでは女性があることをしているように見えると言われています。
何をしている女性に見えるでしょうか?
1.犬の散歩
2.編み物
3.昼寝
+ 答えを見る(こちらをクリック)
2.編み物
インドネシアでは月の模様は『編み物をしている女性』に見えるとされています。
その他にも…アラビアでは『吠えるライオン』、南アメリカでは『ワニ』など国によって見え方は様々です。
第3問
月見は中国から伝わったと言われていますが、いつ頃日本に伝わったでしょうか?
1.平安時代
2.室町時代
3.戦国時代
+ 答えを見る(こちらをクリック)
1.平安時代
月見は、平安時代に中国から日本に伝わって来たと言われています。
平安時代の月見は、酒を飲みながら詩や管弦を楽しむという貴族の楽しみの1つであり庶民には縁が無いものでした。
江戸時代になってから「農作物の豊作祈願と収穫への感謝を表す行事」として庶民の間に広まっていきました。
第4問
月見の際に飾るすすきにはどんな意味があるでしょうか?
1.金運の上昇を祈る
2.魔よけ
3.子の出世を願う
+ 答えを見る(こちらをクリック)
2.魔よけ
すすきの切り口はとても硬く鋭いことから、魔よけの効果があると信じられていました。
月見に供えたすすきを玄関の軒先に飾ると、無病息災につながるとも言われています。
第5問
月見団子にはどのような願いが込められているでしょうか?
1.来年の豊作
2.雨ごい
3.長生きできますように
+ 答えを見る(こちらをクリック)
1.来年の豊作
月見団子は、「米が無事に収穫できたことに感謝し、来年の豊作を願う」ものです。
月の神様であるツクヨミノミコトは農耕の神様でもあったことから、江戸時代は月が信仰の対象でした。
また、月見団子やすすきを用意するようになったのは江戸時代の後期とも言われています。
第6問
1923年(大正12年)9月1日、関東大震災が発生しました。
この震災を教訓として、毎年9月1日は何の日とされているでしょうか?
1.耐震工事の日
2.防災の日
3.備蓄の日
+ 答えを見る(こちらをクリック)
2.防災の日
毎年、9月1日は『防災の日』です。
関東大震災は死者・行方不明者が約10万5000人と、非常に大きな災害でした。
この震災を教訓とした『防災の日』は、地震だけではなく台風や津波などの様々な災害に関する知識を深め、災害に対処する心構えなどを普及するために制定されました。
この日を中心として、全国的に防災訓練などが行われるようになりました。
第7問
秋のお彼岸に供える『おはぎ』と、春のお彼岸に供える『ぼたもち』。
この違いはなんでしょうか?
1.『おはぎ』は粒餡、『ぼたもち』はこし餡を使う
2.『おはぎ』はこし餡、『ぼたもち』は粒餡を使う
3.実はどちらも同じもの
+ 答えを見る(こちらをクリック)
3.実はどちらも同じもの
『おはぎ』と『ぼたもち』は、実はどちらも同じものです。
どちらも、もち米を餡子で包んだものなのになぜ呼び方が違うのかと言うと、季節の花を意識したことが由来と言われています。
春は牡丹(ぼたん)の花が咲くことから『ぼたもち』、秋は萩(はぎ)の花が咲くことから『おはぎ』と呼ばれるようになりました。
第8問
月が密接に関わってくる物語に『竹取物語』があります。
では、この物語の作者は誰でしょうか?
1.夏目漱石
2.紫式部
3.作者は不明
+ 答えを見る(こちらをクリック)
3.作者は不明
竹取物語は、平安時代初期に書かれたと言われていますが、具体的な年・作者は不明です。
現代でも昔話の『かぐや姫』として、絵本やアニメーションなど様々な形で日本人に愛されている作品ですね。
第9問
実は赤とんぼは、大人になったばかりの頃は体が黄色です。
成長する過程でオスのみ、体が赤く変化しますが、それは一体なぜでしょうか?
1.天敵に毒を持っていると思わせるため
2.オスがメスにアピールするため
3.紅葉を食べるので紅葉の色素が体に移るため
+ 答えを見る(こちらをクリック)
2.オスがメスにアピールするため
赤とんぼは「オスがメスにアピールするため」に、オスのみが赤い体に変化すると言われています。
他にも「縄張り争いのため」や「紫外線から身を守るため」とも言われています(赤色は紫外線をカットしやすい色の1つです)。
メスの赤とんぼの場合は生涯黄色いままか、体の一部だけが少し赤くなる程度です。
第10問
9月は瀬戸内海周辺で獲れるマダコが旬の時期です。
では、タコのオスとメスを見分けるポイントはどこでしょうか?
1.目の大きさ
2.足の長さ
3.吸盤
+ 答えを見る(こちらをクリック)
3.吸盤
タコは吸盤に注目すると、オスかメスか簡単に見分けることができます。
メスの吸盤は比較的小さいものが綺麗に2列に並んでいます。
一方オスの吸盤は、大小さまざまなものが不規則に配置されています。オス同士がメスや縄張りを巡って争う際にはこの大きな吸盤が強力な武器になります。
また、メスのタコはオスより身が柔らかいので食べやすく、オスのタコは身がしまっていてメスよりも歯ごたえがあります。
【高齢者向け】9月に関する雑学&豆知識おもしろクイズ問題【中編10問】


博士
前編10問はどうじゃったかのう?まだ物足りないという人は、次の10問にも挑戦してみるのじゃ!
第11問
9月は旧暦で何と言うでしょうか?
1.弥生(やよい)
2.師走(しわす)
3.長月(ながづき)
+ 答えを見る(こちらをクリック)
3.長月(ながづき)
9月は旧暦では、長月と言います。
旧暦の9月は、新暦で言えば10月上旬~11月上旬頃にあたります。
夜がだんだん長くなる時期であるため、『夜長月』と呼ばれていたものが縮まって『長月』になったとの説があります。
第12問
秋が旬の果物であるアケビは、実を食べた後に残った皮があることに使われます。
それは一体何でしょうか?
1.料理
2.タワシの代わり
3.虫よけ
+ 答えを見る(こちらをクリック)
1.料理
アケビの皮は食材として料理にも使われています。アケビは熟すと皮がパカっと割れて、中の身が露出した状態になります。
この実を食べて残った皮は…「挽き肉やキノコ類などを詰めて油で揚げる」「刻んで野菜などと一緒に味噌炒めにする」などして食べられます。
アケビの皮にはニガウリのような苦味がありますが、味噌との相性が良いと言われています。
第13問
9月の誕生石はなんでしょうか?
1.ダイヤモンド
2.サファイア
3.サンゴ
+ 答えを見る(こちらをクリック)
2.サファイア
サファイアは、『慈愛・誠実・貞操』などの意味を持つ9月の誕生石です。
サファイアの名前の由来は、ラテン語で『青』という意味の『サッピールス(sapphirus)』だと言われています。
「王族や君主を危害やねたみから守る」という意味もあったことから、古代より指輪や冠としても重宝された宝石です。
第14問
日本で初めて運動会が開催されたのはいつ頃でしょうか?
1.江戸時代
2.明治時代
3.大正時代
+ 答えを見る(こちらをクリック)
2.明治時代
1874年(明治7年)、東京・築地の海軍兵学寮で日本初の運動会である『競闘遊戯会』が開催されました。
当時の日本にはスポーツという概念はあまり普及していませんでした。学校の授業は殆ど座学であり、体育の授業も武道と馬術くらいでした。
イギリス海軍顧問団の団長として日本に滞在していたアーチボルド・ルシアス・ダグラスがその状況を見て、「勉強ばかりの学生たちのストレスを発散させる手段」として運動を推奨しました。それが『競闘遊戯会』開催へと繋がりました。
第15問
「雷が落ちた所で豊作になる」という言い伝えがある秋の味覚はなんでしょうか?
1.栗
2.サツマイモ
3.キノコ
+ 答えを見る(こちらをクリック)
3.キノコ
キノコは、「雷が落ちた場所で豊作になる」と言われています。
これは単なる迷信ではありません。実際に人工的な稲妻を発生させてキノコに当てたところ、人工的な稲妻を当てていないキノコと比べて約2倍の収穫量になったという結果がでいます。
キノコは菌糸に雷などの衝撃が走ると、一時的に菌糸の働きが停止しますが、その後は逆に非常に活発になることが判明しています。
これは雷によって、命の危機に晒されたキノコが生き延びようとした結果であると考えられています。
第16問
毎年9月1日~30日は、ある病気の予防や早期発見・早期治療を呼び掛ける活動が行われます。
その病名はなんでしょうか?
1.骨折
2.白内障
3.がん
+ 答えを見る(こちらをクリック)
3.がん
毎年9月1日~30日は、『がん征圧月間』です。
日本人の死亡原因第1位は『がん』であり、がんによる死亡者は年々増加しています。
『がん征圧月間』では、がん予防に対する意識啓発を目的として、全国でさまざまな広報活動が行われ、適切な予防や早期発見・早期治療を呼び掛けています。
第17問
現代では人気者ですが、江戸時代では人気が無かった秋の味覚はなんでしょうか?
1.柿
2.サンマ
3.栗
+ 答えを見る(こちらをクリック)
2.サンマ
サンマは、江戸時代では人気が無い魚でした。
当時は淡白な味の物が好まれる傾向にあり、脂がのったサンマを好んで食べることはありませんでした。
サンマが食べられるようになったのは江戸時代後期頃です。
しかし、食べられるようになった理由は人口増加などによる食糧難であり、贅沢を言っていられない庶民が食べる魚という扱いでした。
第18問
干し柿の甘さは砂糖の何倍と言われているでしょうか?
1.砂糖の0.5倍(半分)
2.砂糖の1.5倍
3.砂糖の10倍
+ 答えを見る(こちらをクリック)
2.砂糖の1.5倍
干し柿の甘さは、なんと砂糖の1.5倍と言われています。
あの渋柿がそんなに甘くなるとは驚きですね。
干し柿は水分が蒸発することで大きさが元の柿の3分の1程度になり、元々柿に多く含まれているビタミンCも減ってしまいます。
その代わりにβカロテンやビタミンA、食物繊維などが通常の柿より大幅に増えます。そのため干し柿には、血圧を下げる効果や風邪予防、整腸作用なども期待できます。
第19問
9月に収穫できるウリ科の野菜であるユウガオ。
これを加工することである食品ができますが、それは一体なんでしょうか?
1.かんぴょう
2.メンマ
3.春雨
+ 答えを見る(こちらをクリック)
1.かんぴょう
ユウガオは、かんぴょうの原材料になっています。
名前を聞くとアサガオの仲間のようにも思えますが、全く別の植物です。
また、かんぴょうの生産量日本一は栃木県で、国内生産量の99%程が栃木県産です。
第20問
秋に鳴く虫の1種であるキリギリス。
童話の『アリとキリギリス』の中では、アリが冬に備えて食料を蓄えているのに対し、キリギリスは遊んでばかりの怠け者として描かれています。
では、実際のキリギリスはどうやって冬を越すでしょうか?
1.そもそも冬を越せない
2.大量にエサを食べて春まで冬眠する
3.実はエサを蓄えている
+ 答えを見る(こちらをクリック)
1.そもそも冬を越せない
キリギリスは、そもそも冬を越すことができません。
秋~冬の初めにかけて繁殖を行い、本格的な冬を迎える前には死んでしまいます。
キリギリスに限らず秋の虫の中で鳴くのは、ほぼオスのみです。キリギリスのようなオスの秋の虫が鳴くのはメスにアピールするためです。
つまり、キリギリスが鳴いているのは童話のように遊んでいるわけではなく、命が尽きる前に子孫を残そうとしているからです。
【高齢者向け】9月に関する雑学&豆知識おもしろクイズ問題【後編10問】


博士
中編10問はどうじゃったかのう?「まだまだ物足りない!」という人は、次の10問にも挑戦してみるのじゃ!
第21問
9月の星座はどれでしょうか?
1.おとめ座
2.さそり座
3.みずがめ座
+ 答えを見る(こちらをクリック)
1.おとめ座
8月23日~9月22日までに生まれた人は「おとめ座」、9月23日~10月23日までに生まれた人は「てんびん座」となっています。
第22問
9月8日頃を指す言葉はどれでしょうか?
1.赤露
2.白露
3.秋露
+ 答えを見る(こちらをクリック)
2.白露
秋になると夜間に気温が下がり、大気中の水蒸気が草花に朝露となって付着するようになります。
「光によって白く見える露ができ始める時期」という意味で「白露」となったと言われています。
第23問
9月4日は、有名なテーマパークの開園記念日です。
そのテーマパークはなんでしょうか?
1.ユニバーサル・スタジオ・ジャパン
2.志摩スペイン村
3.東京ディズニーシー
+ 答えを見る(こちらをクリック)
3.東京ディズニーシー
2001年(平成13年)9月4日、千葉県浦安市舞浜に東京ディズニーシーが開園しました。
現在も多くの人が訪れる日本を代表するテーマパークの1つです。
第24問
次のうち、秋の七草ではない植物はどれでしょうか?
1.ススキ
2.オミナエシ
3.コスモス
+ 答えを見る(こちらをクリック)
3.コスモス
秋の七草は、ハギ・ススキ・クズ・カワラナデシコ・オミナエシ・フジバカマ・キキョウの7つです。
コスモスは秋を代表する花の1つですが、秋の七草ではありません。
第25問
栗のイガの中には本来いくつの栗が入っているでしょうか?
1.1個
2.3個
3.5個
+ 答えを見る(こちらをクリック)
2.3個
本来は1つのイガの中には、3個の栗が入っているものです。
イガの中に1つしか栗が入っていない品種もありますが、それは栽培技術の発展によって生まれた品種です。
第26問
丹波栗は、昔の丹波国(現在の京都府中部、兵庫県東辺の一部、大阪府北辺の一部)から広まって行った品種です。
全国的に有名になったきっかけはなんでしょうか?
1.天保の飢饉
2.参勤交代
3.明治維新
+ 答えを見る(こちらをクリック)
2.参勤交代
丹波栗は、古事記や万葉集などにもその存在が記されている非常に歴史のある栗です。
江戸時代に京都周辺で人気となり、参勤交代で全国に広まっていったと言われています。
第27問
9月14日は「メンズバレンタインデー」です。
男性から女性にあるものを贈って告白する日とされていますが、何を贈る日でしょうか?
1.下着
2.キッチン用品
3.化粧品
+ 答えを見る(こちらをクリック)
1.下着
メンズバレンタインデーは、男性から女性に下着を贈って告白する日だとされています。
「日本ボディファッション協会」という日本を代表する婦人用インナーウエアとナイトウエアのメーカー団体が定めた記念日です。
しかし、知名度はかなり低く男性にとって女性に下着を贈るという行為のハードルの高さからかほとんど浸透していません。
第28問
9月21日は、とある病気の啓蒙活動が行われる日です。
その病気とはなんでしょうか?
1.関節リウマチ
2.認知症
3.心不全
+ 答えを見る(こちらをクリック)
2.認知症
1994年「国際アルツハイマー病協会(ADI)」は、「世界保健機関(WHO)」と共同で毎年9月21日を「世界アルツハイマーデー」と制定し、この日を中心に認知症の啓蒙を実施しています。
また、9月は「世界アルツハイマー月間」と定められており、様々な取り組みを行っています。
みなさんのお住いの地域でも、9月になると認知症に関する市民向けの講座が開催されるなど様々な活動が行われているかもしれません。
気になる方は市の広報などをチェックしてみましょう。
第29問
「ノアの箱舟」の主人公ノアが栽培したと言われている秋の味覚はなんでしょうか?
1.ブドウ
2.柿
3.サツマイモ
+ 答えを見る(こちらをクリック)
1.ブドウ
「ノアの箱舟」の物語では、動物たちと共に洪水から生き延びたノアが葡萄(ブドウ)を栽培する描写があります。
葡萄の歴史はとても古く、紀元前3500年頃のメソポタミア文明の頃の記録が人類の葡萄栽培における最古の記録だと言われています。
第30問
レンコンは節がある野菜です。
最も柔らかいのはどの節でしょうか?
1.1節目
2.2節目
3.3節目
+ 答えを見る(こちらをクリック)
1.1節目
レンコンは育つ過程で多くて6つ程の節ができますが、5節目6節目は他の節に栄養を取られてしまいます。
そのため、市場に出回るのは3~4節目までがついたレンコンです。
鳥のくちばしのような芽がついている丸っこいのが1節目であり、繊維が細くて柔らかいのが特徴です。 そのため、サラダにしても美味しく食べられます。
逆に3~4節目は堅く繊維立っているのが特徴です。食感を活かす楽しみ方もできる部分であり、煮物やきんぴらに適しています。
2節目は1節目と3~4節目の中間くらいの柔らかさです。

博士
今回のクイズ問題は以上じゃ!君は何問解けたかな?
このサイトではいろんな脳トレクイズを紹介しているから、ぜひ他のクイズにも挑戦してみるのじゃ!